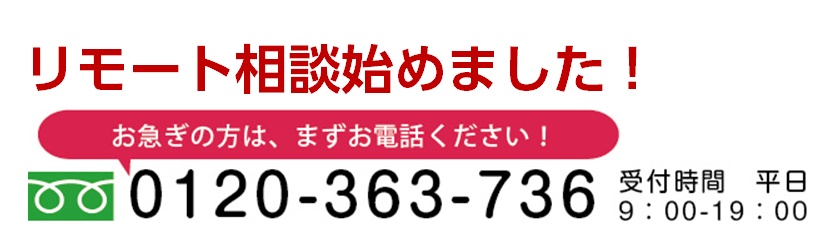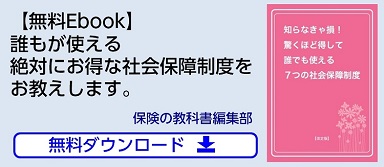「給料は上がっているはずなのに、なぜか手取りが増えない…」「社会保険料が、いつの間にか高くなっている気がする」
多くの人が、このような実感を持っているのではないでしょうか。その原因は、私たちが気づかないうちに、静かに、そして着実に進められている「ステルス増税」にあるかもしれません。
「税金」という直接的な名前を巧みに避け、「社会保険料」や「支援金」、「拠出金」といった様々な名目で、私たちの可処分所得は少しずつ削り取られています。
本記事では、すでに始まっている、そしてこれから予定されているステルス増税の具体的な中身を一つひとつ解き明かし、この静かなる国民負担増の波に、私たちがどう向き合っていくべきかを解説します。
The following two tabs change content below.
「ステルス増税」とは何か?その巧妙な3つの手口
ステルス増税とは、戦闘機がレーダーに映らないように飛行する「ステルス」の名の通り、国民に「増税」であると意識させにくい形で、実質的な負担を増やしていく手法を指します。その手口には、主に3つの特徴があります。
- 「税」という言葉を使わない:「社会保険料」「子育て支援金」「森林環境税」など、税金とは異なる名目を使うことで、増税に対する国民の心理的抵抗感を和らげます。
- 少額から始める:年間1,000円、月額数百円といった、一見すると些細な金額から導入します。国民がその負担に慣れた頃を見計らって、段階的に金額を引き上げていくケースが少なくありません。
- 複雑な制度変更に紛れ込ませる:社会保障制度全体の改正や、他の非課税措置の終了といったタイミングに合わせて導入することで、国民の注意を逸らし、変更点を分かりにくくします。
【すでに始まっている】主なステルス増税の具体例
では、実際にどのようなステルス増税が、すでに私たちの生活に影響を与えているのでしょうか。代表的な例を見ていきましょう。
(1)住民税と社会保険料における負担増
私たちの給与から天引きされる項目の中で、近年、静かに負担が増しているのが住民税と社会保険料です。
- 森林環境税(2024年度~):2024年度から、住民税と合わせて年間1,000円が徴収されています。これは、2023年度まで徴収されていた「復興特別住民税(1,000円)」と入れ替わる形のため、年間の合計負担額は変わりませんが、「森林保全」という新たな目的のための国民負担が、静かに始まっています。
- 介護保険料・後期高齢者医療保険料の引き上げ:少子高齢化を背景に、65歳以上の介護保険料や75歳以上の後期高齢者医療保険料は、定期的に見直され、段階的に引き上げられています。月額数百円単位の変更であるため気づきにくいですが、着実に負担は増しています。
- 社会保険の適用拡大(106万円の壁の事実上撤廃):これまで社会保険の加入義務がなかった短時間労働者(パート・アルバイト)の適用が、段階的に拡大されています。今後は企業の規模を問わず、「週20時間以上」働く人は加入が必須となる方向です。これにより、新たに保険料負担(給与の約15%)が発生する人が大幅に増加します。
(2)贈与・相続に関する課税強化
資産移転に関する非課税措置の縮小や、課税強化も進んでいます。
- 結婚・子育て資金の一括贈与非課税の廃止:祖父母や親から子・孫へ、結婚や子育てのための資金を最大1,000万円まで非課税で贈与できる特例が、2025年3月末をもって廃止されました。
- 生前贈与の相続税への加算期間延長:亡くなる直前の駆け込み贈与による相続税逃れを防ぐため、相続財産に加算される生前贈与の期間が、死亡前「3年」から「7年」へと大幅に延長されました。
(3)インボイス制度による実質的な負担増
2023年10月から始まったインボイス制度は、消費税率そのものを変えるものではありません。しかし、これまで消費税の納税が免除されていた多くの小規模事業者(免税事業者)が、取引を維持するために課税事業者となり、新たに消費税を納税する必要に迫られました。これは、納税者の範囲を広げることによる、実質的な増税と言えます。
【今後予定される】さらなるステルス増税の波
現在、政府の税制調査会などでは、さらなる負担増に繋がる様々な議論が行われています。これらが、いつ、どのような形で私たちの生活に影響してくるか、注視していく必要があります。
サラリーマン・経営者を狙い撃ち?通勤手当・退職金への課税
- 通勤手当への課税:現在、一定額まで非課税とされている電車代やガソリン代などの通勤手当を、給与と同じように課税対象としてはどうか、という議論があります。
- 退職所得課税の見直し:退職金は、長年の功労に報いるため税制上大きく優遇されていますが、この優遇措置(特に勤続20年超での控除額の増額)を縮小し、課税を強化しようという動きが長年くすぶっています。
すべての国民に関わる新たな税負担
- 走行距離税:電気自動車(EV)の普及により、ガソリン税の税収が減少することを見据え、自動車の走行距離に応じて課税する「走行距離税」の導入が検討されています。
- 専業主婦(第3号被保険者)への社会保険料課税:現在、厚生年金に加入する配偶者の扶養に入っている専業主婦(主夫)は、保険料の負担なく国民年金に加入できますが、この「第3号被保険者制度」を見直し、何らかの保険料負担を求めるべきだという議論があります。
なぜステルス増税は行われるのか?政策の矛盾
ここで大きな疑問が浮かびます。政府は、定額減税や賃上げ促進税制などで「国民の手取りを増やす」政策をアピールしている一方で、なぜ、その効果を相殺するような実質的な負担増を、次々と進めるのでしょうか。
その背景には、「財務省(税金)」と「厚生労働省(社会保険)」の縦割り行政の問題があります。財務省は「減税」で国民の支持を得たいと考える一方で、厚生労働省は、年々膨張する医療・年金財源を確保するために「社会保険料」の徴収を強化せざるを得ません。
国民から見れば、税金で引かれようが、社会保険料で引かれようが、「手取りが減る」という現実は同じです。しかし、省庁間の連携が取れず、それぞれが別々のロジックで動くため、結果として、国民生活に大きな混乱と、静かなる負担増をもたらしているのです。
私たちにできる唯一の対抗策
では、このステルス増税の大きな流れに、私たち個人はどう対抗すれば良いのでしょうか。個別の節税対策も重要ですが、より本質的な対策は「知ること」そして「意思表示をすること」に尽きます。
国の政策は、私たちが知らないうちに、水面下で議論され、決定されていきます。そして、一度決まったことを覆すのは、極めて困難です。
だからこそ、日頃から税制や社会保障制度の改正のニュースに関心を持ち、「なぜこの制度が変わるのか」「自分の生活にどう影響するのか」を正しく理解しようと努めることが、まず第一歩となります。
そして、その上で、選挙の際に、各政党がどのような方針を掲げているのかを比較検討し、自らの考えに近い政策を支持する一票を投じる。民主主義国家において、これが、私たち国民に与えられた、唯一かつ最も強力な対抗策なのです。
まとめ
私たちの手取りは、気づかぬうちに様々な名目で少しずつ削り取られているのが、今の日本の現実です。その多くは、「税金」という分かりやすい名前ではなく、複雑な制度変更の中に巧みに隠されています。
この状況をただ嘆くのではなく、まずはその実態を正しく知り、社会全体の動向に関心を持つことが、自身の資産を守るための第一歩となります。賢い納税者、そして賢い主権者として、国の政策と向き合っていく。その姿勢こそが、これからの不透明な時代を生き抜くための、最も確かな「資産防衛術」と言えるでしょう。
この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。さらに詳しい内容について知りたい場合に、参考にしてください。