次のようなことでお悩みではありませんか?
・自分にピッタリの保険を選んで加入したい
・現在加入中の保険の内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
・どんな保険に加入すればいいのか分からない
もしも、保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
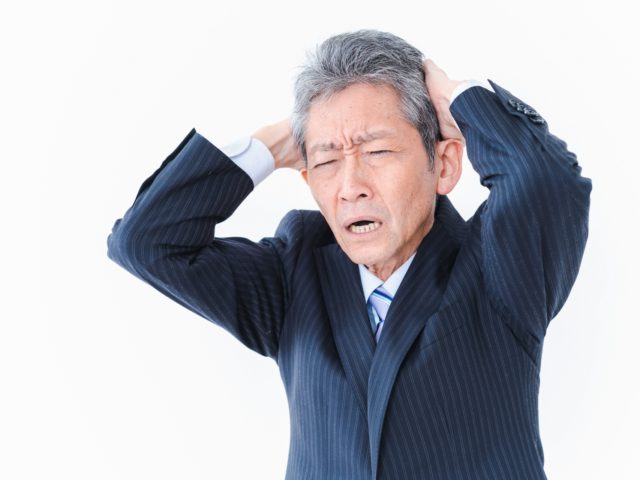
老後資金を準備するための有力な手段として、多くの方が活用しているiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)。掛金が全額所得控除になるなど、税制上の大きなメリットがあることから、将来のためにコツコツと積立を続けている方も多いでしょう。
しかし、2025年度(令和7年度)税制改正により、その「出口」である受取時の税制優遇ルールが、多くの人にとって不利になる、いわば「大改悪」とも言える変更が行われることが決定しました。
これは、特に会社の退職金とiDeCoを併用して受け取る予定だった方にとって、将来の手取り額が想定より大幅に減少しかねない重要な変更です。
この記事では、まずiDeCoの基本的なメリットを再確認し、これまでの受け取りに関する税制ルール、そして今回どのようにルールが改悪されたのか、さらにその改悪に対する具体的な対策について詳しく解説していきます。
社長の資産防衛チャンネル編集チーム
最新記事 by 社長の資産防衛チャンネル編集チーム (全て見る)
目次
iDeCoは、公的年金(国民年金・厚生年金)に上乗せして給付を受けられる私的年金制度の一つです。
自分で掛金を拠出し、用意された投資信託などの金融商品で運用、その成果を原則60歳以降に受け取ることで、老後資金を形成します。国が老後資産形成を後押しするために設けた制度であり、税制面で非常に大きな優遇措置が講じられています。
iDeCoの最大のメリットは、毎月の掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の所得から控除されることです。これにより、所得税・住民税の負担が軽減されます。
例えば、課税所得500万円の方が毎月2万円(年間24万円)を拠出した場合、所得税・住民税合わせて年間約7.2万円(税率30%と仮定)もの節税効果が期待できます。
掛金の上限額は、加入者の職業や他の年金制度への加入状況によって異なります(例:自営業者は月額6.8万円、企業年金のない会社員は月額2.3万円など)。
2024年12月からは、確定給付企業年金(DB)等に加入している方のiDeCo拠出限度額の計算方法が見直され、一部の方で拠出可能額が増えるといった改正も行われています。
通常、株式や投資信託の運用で得た利益(配当、分配金、譲渡益)には、20.315%の税金がかかります。
しかし、iDeCoの口座内で得た運用益はすべて非課税となり、そのまま再投資されます。長期間の運用では、この非課税メリットと複利効果により、資産を効率的に増やすことが期待できます。
原則60歳以降に受け取る際にも、税制上の優遇措置が用意されています。
受け取り方は「一時金」「年金」「両方の併用」から選べ、それぞれに大きな控除が適用されます。今回の「改悪」は、この受け取り時のルールに関するものです。
まず、iDeCoの受け取り方と、それぞれに適用される税制優遇を確認しておきましょう。
多くの場合、退職所得控除のメリットが大きいため、一時金での受け取りが有利とされてきました。
ここで問題となるのが、会社の退職金とiDeCoの一時金を両方受け取る場合です。
退職所得控除は、その年に受け取る退職所得全体に対して適用されます。もし同じ年に会社の退職金とiDeCoの一時金を受け取ると、両方の合計額に対して一つの退職所得控除しか使えず、控除枠を超えた部分に課税されてしまいます。
これを避けるために、受け取る年をずらすという方法が考えられます。しかし、この場合にも、短期間に複数の退職金を受け取ることで過度な税優遇を受けることを防ぐため、控除額を調整するルールが存在します。
従来のルールでは、退職金を受け取る年の前年以前「4年以内」に、他の退職金(iDeCoの一時金など)を受け取っていた場合、それぞれの勤続期間(加入期間)のうち、重複している期間については、後から受け取る退職金の退職所得控除額が調整(減額)されることになっていました。
これを回避するためには、受け取るタイミングを5年以上空ける必要があったため、一般に「5年ルール」と呼ばれていました。
例えば、60歳でiDeCoの一時金を受け取り、65歳で会社の退職金を受け取る、といったプランであれば、5年間の間隔が空いているため、それぞれの退職所得控除を最大限に活用できていました。 (※ちなみに、iDeCoと他の確定拠出年金の一時金を両方受け取る場合は、さらに厳しい「19年ルール(前19年以内)」が適用されます。)
ここからが本題です。2025年度(令和7年度)税制改正により、この「5年ルール」が大幅に改悪されることが決定しました。
結論から言うと、退職所得控除の重複調整の対象となる期間が、「前年以前4年以内」から「前年以前9年以内」に延長されます。
これにより、退職所得控除をそれぞれ満額活用するためには、iDeCoの一時金と会社の退職金の受け取りタイミングを、10年以上空ける必要が生じることになったのです。
この改正は、多くの会社員の退職プランに大きな影響を与えます。
例えば、これまで一般的だった「60歳でiDeCoを受け取り、65歳定年時に会社の退職金を受け取る」というプランでは、受け取り間隔が5年しかなく、新たな「10年ルール」に抵触してしまいます。
その結果、後から受け取る会社の退職金にかかる退職所得控除額が大幅に減額され、手取り額が大きく減少してしまうことになるのです。
60歳でiDeCoを受け取った場合、会社の退職金で控除を満額使うためには、70歳まで退職を待たなければならない、という状況が生まれます。
さらに大きな問題は、原則60歳まで資金がロックされるiDeCoのような制度で、後から加入者にとって不利なルール変更が行われたという前例ができてしまったことです。
2024年度の税制改正議論では、退職所得控除そのものの縮小案(勤続20年超の控除額引き下げ)も検討されていました(今回は見送り)。今後も、国の財政状況などによっては、さらなる改悪が行われる可能性も否定できません。
では、この厳しいルール変更に対して、私たちはどのような対策を取ることができるのでしょうか。
最もシンプルですが、実行が難しい対策です。
iDeCoの受け取りを60歳で行うのであれば、会社の退職金は70歳以降に受け取る。あるいは、会社の退職金を60歳で受け取るのであれば、iDeCoの受け取り開始を70歳以降に遅らせる(iDeCoは75歳まで受取開始を繰下げ可能)といった方法です。
しかし、多くの方のライフプランとは合わない可能性があります。
今回の改正は、あくまで「一時金」で受け取る際の退職所得控除に関するものです。
「年金」として分割で受け取る場合は、このルールの影響を受けません。年金受取の場合は「公的年金等の雑所得」として扱われ、「公的年金等控除」が適用されます。
会社の退職金で退職所得控除の枠を使い切ってしまうような場合は、iDeCoは年金で受け取る、という選択が有力になります。
金融機関によっては、iDeCoの受け取り方を「一部を一時金、残りを年金」と併用できる場合があります。
会社の退職金とiDeCoの一時金を合わせても、退職所得控除の枠内に収まる(あるいは少し超える程度)ように、iDeCoの一時金の額を調整し、残りを年金で受け取るという方法です。
これにより、税負担を最小限に抑えつつ、まとまった資金も確保できる可能性があります。
どの方法が最適かは、会社の退職金の額、iDeCoの積立額、そしてご自身のライフプランによって異なります。ご自身の状況を正確に把握し、税額をシミュレーションした上で、最適な受け取り方を検討することが重要です。
iDeCoは、掛金の全額所得控除、運用益の非課税、そして受取時の控除と、3段階で税制優遇が受けられる非常に優れた老後資産形成制度です。
しかし、2025年度税制改正により、一時金で受け取る際の「退職所得控除」に関するルールが改悪され(いわゆる「5年ルール」が「10年ルール」へ)、会社の退職金と併用する際の出口戦略がより難しくなりました。
これを知らずにいると、将来の税負担が想定以上に重くなる可能性があります。
対策としては、受け取り時期を10年以上空ける、iDeCoを年金形式で受け取る、あるいは一時金と年金を併用するといった方法が考えられます。
原則60歳まで資金が拘束される制度において、後から加入者に不利なルール変更が行われたことは、制度への信頼を揺るがしかねない大きな問題です。
今後のさらなる制度変更の可能性にも注意を払いながら、ご自身の退職プランと照らし合わせて、最適な出口戦略を早めに検討しておくことが、これまで積み立ててきた大切な資産を守る上で不可欠と言えるでしょう。
この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な計算例やさらに詳しい対策について知りたい場合に、参考にしてください。
次のようなことでお悩みではありませんか?
・自分にピッタリの保険を選んで加入したい
・現在加入中の保険の内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
・どんな保険に加入すればいいのか分からない
もしも、保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

日本では、民間保険に入らなくても、以下のように、かなり手厚い保障を受け取ることができます。
多くの人が、こうした社会保障制度を知らずに民間保険に入ってしまい、 気付かないうちに大きく損をしています。
そこで、無料EBookで、誰もが使える絶対にお得な社会保障制度をお教えします。
ぜひダウンロードして、今後の生活にお役立てください。

法人名義での投資信託|個人とは違う5つのメリットと注意点を解説
新NISA制度の開始などをきっかけに、個人の資産運用への関心が急速に高まっています。その中でも「投資信託」は、専門家が運用を行う手軽さから、多くの方が活用している金融商品です。では、この投資信託を、個人としてではなく、会社(法人)として運用することに、どの

【2025年度税制改正】iDeCoの出口戦略に激震!受取時の増税「10年ルール」とは?
老後資金を準備するための有力な手段として、多くの方が活用しているiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)。掛金が全額所得控除になるなど、税制上の大きなメリットがあることから、将来のためにコツコツと積立を続けている方も多いでしょう。 しかし、2025年

つみたてNISAは、少額で始められる投資として人気があります。 投資信託と同じ仕組みですが、非課税制度があり、手数料もおさえられているので、投資未経験者や初心者の方におすすめとされています。 ただ、実際につみたてNISAを始めようと思っても、金

会社員にもおすすめ!今最も節税できる個人型確定拠出年金iDeCoの全知識
お金を増やしたい、税金をできるだけ抑えたいと誰もが思うのではないでしょうか。 その両方が叶えられるのが、個人型確定拠出年金iDeCoです。ふるさと納税をしのぐ節税手段であり、将来のお金を貯めていくのにはNISAよりもお得な制度といってもいいでしょう。

個人型確定拠出年金とは?押さえておくべき税制メリットと注意点
みなさんは確定拠出年金という制度をご存知ですか? 確定拠出年金は、公的年金に上乗せできる私的年金の制度のことをいい、大きくは「企業型」と「個人型」の2つに分かれています。その中でも個人型確定拠出年金(愛称iDeCo(イデコ)は、平成29年1月に大きな

2017年1月より、個人型確定拠出年金、通称iDeCo(イデコ)の加入範囲が拡大し、60歳未満の方であれば、ほとんど全ての方が加入の対象となりました。2018年8月末時点で100万人を突破しており、年々増加の傾向にあります。 個人型確定拠出年金は、税

iDeCo(イデコ)の正式名称は「個人型確定拠出年金」と言います。 数年前に「老後2,000万円問題」が話題となりましたが、老後の資産形成をするための選択肢として注目されました。 毎年のように加入者は増えていますが、実際にiDeCoを初めている