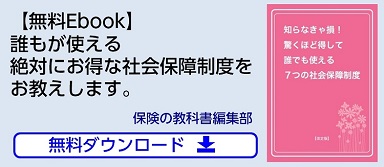長年かけて大切に育て上げてきた会社を、いずれは後継者である子どもに引き継いでほしい。そう願うオーナー経営者にとって、避けては通れない大きな壁が、事業承継に伴う「税金」の問題です。
特に、業績が好調で、内部留保が厚い優良企業であるほど、会社の価値、すなわち「自社株の評価額」は高騰します。この高額な自社株を後継者に贈与または相続させる際には、想像を絶するような贈与税や相続税が課される可能性があり、後継者が納税資金を準備できずに、最悪の場合「黒字廃業」を選択せざるを得ないケースも少なくありません。
では、この深刻な「自社株問題」を、どうすれば解決できるのでしょうか。その答えは、「計画的に、合法的な方法で、一時的に自社株の評価額を引き下げる」ことにあります。そして、そのための極めて強力なツールとなるのが、航空機や船舶などを活用した「オペレーティング・リース」という金融スキームです。
この記事では、まず事業承継における自社株問題の本質を解説し、その上で、オペレーティング・リースがなぜ株価対策の切り札となり得るのか、その仕組みと、具体的な事業承継スキーム、そして活用する上での注意点について詳しくご紹介していきます。
The following two tabs change content below.
1.事業承継における「自社株問題」とは?
なぜ自社株の評価が高いと問題なのか?
非上場会社である中小企業の自社株は、その評価額が、会社の純資産(資産から負債を引いたもの)や利益額などに連動して算出されます。したがって、業績が良い会社ほど、自社株の評価額は高くなります。
後継者がこの価値の高い自社株を先代経営者から引き継ぐ際、生前であれば「贈与税」、相続であれば「相続税」の課税対象となります。株価が高ければ高いほど、その税負担は雪だるま式に増加し、時には数億円単位の納税が必要になることもあります。
なぜ自社株の売却は解決策にならないのか?
「それなら、株を売却して現金化すれば、納税資金に充てられるのでは?」と考えるかもしれません。しかし、これには2つの大きな問題点があります。
- (1)換金性が極めて低い:日本の株式会社の99%以上を占める非上場株式には、上場株式のような公的な取引市場が存在しません。そのため、買い手を見つけることは極めて困難であり、自社株は「換金性の乏しい財産」と言えます。
- (2)経営権を危うくする:仮に買い手が見つかったとしても、自社株を安易に社外へ売却することは、会社の「経営権の分散」を意味します。特に、会社の重要事項に対する拒否権を持つことができる「3分の1」以上の株式が外部に流出すれば、経営の安定性が著しく損なわれるリスクがあります。
これらの理由から、事業承継を円滑に進めるためには、自社株の売却ではなく、「経営に支障をきたさない範囲で、自社株の評価額そのものを、引き継ぐタイミングで引き下げる」という対策が、極めて重要になるのです。
2.株価対策の切り札「オペレーティング・リース」の仕組み
そこで、自社株の評価額を計画的に引き下げるための有効な手段として活用されるのが、「オペレーティング・リース」への出資です。
オペレーティング・リースとは?
オペレーティング・リースとは、航空機や船舶、海上コンテナといった、中古市場でも価値が下がりにくい高額な資産(リース物件)のリース事業に、投資家(この場合は会社)が出資する金融取引です。出資した会社は、リース期間中に得られる賃貸料(リース料)や、期間満了時の物件売却による利益を、出資持分に応じて分配金として受け取ります。
なぜ株価を下げられるのか?
オペレーティング・リースが株価対策として機能する最大の理由は、出資した初年度に、出資額の70~80%といった非常に大きな会計上の損失(損金)を、合法的に作り出せる点にあります。
この仕組みの鍵は「レバレッジ」です。リース物件は、出資者からの出資金だけでなく、金融機関からの多額の借入金を組み合わせて購入されます。これにより、出資者は、自身の出資額をはるかに上回る規模の資産(リース物件)の減価償却効果を得ることができるのです。この多額の減価償却費が、初年度のリース料収入を大きく上回るため、会計上、大きな損失が計上されることになります。
この損失は、会社の決算において「特別損失」として扱われます。特別損失は、本業の業績とは直接関係のない、一時的な損失であるため、これが計上されたからといって、金融機関からの信用格付けが直ちに悪化する可能性は低いとされています。
つまり、オペレーティング・リースを活用することで、金融機関からの評価を大きく損なうことなく、会社の純資産を一時的に大幅に圧縮し、それに連動する自社株の評価額を、計画的に引き下げることができるのです。
3.【実践編】オペレーティング・リースを活用した事業承継スキーム
では、具体的にどのようにオペレーティング・リースを事業承継に活用するのでしょうか。その流れは、大きく3つのステップに分かれます。
ステップ1:利益の繰延べ(株価の引き下げ)
- 会社に大きな利益が出た事業年度に、オペレーティング・リースへ出資します。
- 出資により、初年度に多額の損失(損金)が計上され、会社の利益が圧縮されます。
- 会社の純資産が減少し、自社株の評価額が大幅に下がります。
ステップ2:自社株の移転
- 自社株の評価額が低くなった、この絶好のタイミングで、先代経営者から後継者へ、贈与または相続により自社株を移転します。
- 株価が低いため、後継者が負担する贈与税・相続税を、大幅に抑えることができます。
- この段階では、先代経営者はまだ代表取締役として経営を継続します。
ステップ3:出口戦略(退職金の活用)
- オペレーティング・リースのリース期間(通常7~10年程度)が満了するのを待ちます。
- 期間が満了すると、リース物件が売却され、出資金が分配金(益金)として会社に戻ってきます。
- この多額の利益(益金)が計上されるタイミングに合わせて、先代経営者が勇退し、会社から「役員退職金」を受け取ります。
役員退職金は、法人にとっては多額の損金となります。これにより、オペレーティング・リースから戻ってきた利益と、退職金の支払費用が相殺され、法人税の負担を最小限に抑えることができます。さらに、受け取る先代経営者にとっても、退職金は給与などと比べて税制面で非常に優遇されているため、効率的に個人資産を形成できるのです。
4.オペレーティング・リース活用の注意点とリスク
このスキームは非常に強力ですが、実行にあたっては、以下の注意点やリスクを十分に理解しておく必要があります。
①資金の長期拘束
オペレーティング・リースへの出資は、原則としてリース期間中(5年~10年以上)の中途解約ができません。一度出資すると、その資金は長期間にわたって拘束されることになります。事業承継という長期的な計画の中で、会社のキャッシュフローを圧迫しないよう、余裕資金で取り組むことが大前提です。
②為替リスクと元本割れ
航空機や船舶を対象とする案件の多くは、米ドル建てで取引されます。そのため、出資時よりも、期間満了時の為替レートが円高ドル安に振れた場合、円ベースでの受取額が目減りし、元本割れする可能性があります。もちろん、逆に円安に振れれば為替差益が期待できますが、この為替リスクは常に念頭に置く必要があります。
③案件の希少性
オペレーティング・リースは人気が高く、優良な案件は、情報が出てからすぐに売り切れてしまうことが珍しくありません。「決算が近いから、今すぐ出資したい」と思っても、希望のタイミングで、希望の条件の案件が見つかるとは限らない、という問題があります。活用を検討する場合は、早めに専門家や取扱会社に相談し、情報を得られる体制を整えておくことが重要です。
まとめ
業績が好調なオーナー企業にとって、高騰した自社株の評価額は、円滑な事業承継を阻む大きな壁となります。「オペレーティング・リース」は、そのレバレッジ効果を利用して、出資初年度に会計上の大きな損失を作り出し、会社の純資産と株価を一時的に引き下げるための、極めて有効な手段です。
株価が下がったタイミングで、後継者へ低い税負担で自社株を移転する。そして、リース期間満了時に戻ってくる利益を、先代経営者への「役員退職金」の支払いとぶつけることで、税負担を相殺する。この一連の流れは、計画的に実行すれば、事業承継における税金問題を解決する、まさに「究極のスキーム」となり得ます。
しかし、その一方で、資金の長期拘束や為替リスクといった、投資としての側面も併せ持っています。この強力な手法を成功させるためには、その仕組みとリスクを十分に理解し、信頼できる専門家と共に、長期的な視点で綿密な計画を立てることが不可欠です.
この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。