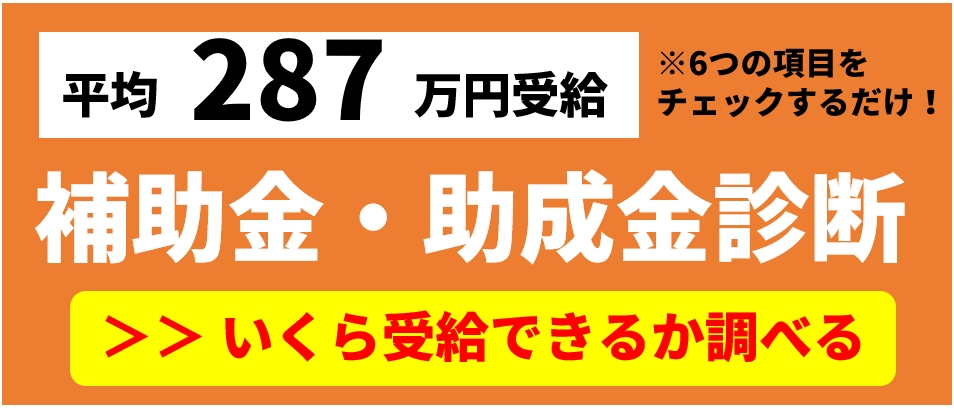「うちにはそんなに財産はないから、相続税は関係ない」「現金で少しずつ贈与しておけば、税務署には分からないだろう」もし、あなたがそのようにお考えであれば、その認識はもはや通用しない時代になったことを知っておく必要があります。相続税の税務調査にAI(人工知能)が本格導入され、これまで見過ごされてきた申告漏れや、巧妙に隠されたつもりの財産が、いとも簡単に発見される時代が到来するからです。
AI調査官は、私たちの何を、どこまで見ているのでしょうか。本記事では、AIによる税務調査の驚くべき仕組みと、それに伴うリスク、そして私たちが今から準備すべき対策について詳しく解説します。
The following two tabs change content below.
「AI税務調査」とは?
相続税の税務調査で、AIを活用したシステムの本格運用を開始します。これは、単なるデジタル化ではなく、税務調査のあり方を根底から変える、非常に大きな変化です。
なぜAIが導入されるのか?所得税調査での実績
この動きの背景には、先行してAIが導入された所得税調査での目覚ましい実績があります。
国税庁は、2023年分の所得税の調査からAIを試験的に導入しました。その結果、税務調査官が現地に赴く実地調査の件数は減少したにもかかわらず、申告漏れなどから追徴した税額は前年比で30億円も増加したのです。これは、AIが人間では見つけきれなかった「怪しい申告」を、極めて高い精度で抽出し、調査の効率と効果を劇的に向上させたことを意味します。この成功を受け、国税庁は満を持して相続税の分野にもAIを投入することを決定しました。
AIは申告書の何を「スコアリング」するのか
では、AI調査官は具体的に何を行っているのでしょうか。その仕組みは、膨大なデータの分析と「スコアリング」にあります。
(1)データの読み込み
まず、AIは全国から提出された相続税申告書はもちろん、過去何十年にもわたる申告漏れのあったデータ、個人の確定申告書、財産債務調書、国外財産調書など、国税庁が持つありとあらゆるデータを学習します。
(2)「申告漏れの傾向」のパターン化
次に、AIは学習したデータから、「どのような資産状況の人が、どのような財産を申告から漏らしやすいのか」という無数のパターンを分析・学習します。例えば、「このくらいの所得がある人は、これくらいの金融資産を持っているはずだ」といった推計も行います。
(3)スコアリングと調査対象の選定
そして、新たに提出された申告書の内容をこれらのパターンと照合し、申告漏れの疑わしい度合いを点数化(スコアリング)します。このスコアが高い申告書、つまりAIが「怪しい」と判断したものが、優先的に税務調査の対象としてリストアップされるのです。
これは、ベテラン調査官の「勘」や「経験」を、AIがデータに基づいてシステム化したものと言え、調査の網はこれまで以上に広く、深くなることを意味します。
AI調査官に見抜かれる!3つの危険なポイント
AIの導入により、特に以下の3つのようなケースは、極めて高い確率で申告漏れを指摘されることになると考えられます。
ポイント①:家族名義の「隠し財産(名義預金)」
「妻や子の名義の預金口座に資金を移しておけば、自分の財産ではないから相続税はかからない」という考えは、もはや通用しません。
AIは、亡くなった本人(被相続人)だけでなく、その配偶者や子、孫など、家族全員の金融機関の口座情報を紐づけて分析します。これにより、例えば「収入のない専業主婦の口座に、夫から毎年多額の入金がある」「働いていない学生の子供の口座に、不相応な残高がある」といった不自然な資金の流れを瞬時に検知します。
たとえ口座の名義が家族であっても、その原資が被相続人から来たものであり、実質的に被相続人が管理していたと判断されれば、それは「名義預金」として相続財産に加算され、追徴課税の対象となります。
ポイント②:生前の「暦年贈与」の申告漏れ
年間110万円までの贈与が非課税となる「暦年贈与」は、一般的な相続対策として知られています。しかし、この制度を正しく理解せずに行っているケースが後を絶ちません。
例えば、毎年110万円ずつ10年間にわたって贈与していても、贈与契約書を作成していなかったり、贈与のたびに資金を移動させていなかったりすると、税務署から「それは10年前に1,110万円を贈与する約束を分割で実行しただけ(連年贈与)」と見なされ、多額の贈与税を課されるリスクがあります。
AIは、親子間や祖父母と孫の間で行われた数百万、数千万円単位の預金の移動を自動で検知します。贈与税の申告が伴っていない場合、その資金移動の理由について、厳しいお尋ねが来る可能性が非常に高まります。
ポイント③:「タンス預金」などの現金資産
「現金で自宅に保管しておけば、税務署には分からないだろう」という「タンス預金」も、AIの前では無力です。
AIは、被相続人の過去の所得税申告書などから生涯の収入を把握し、そこから生活費などの推定支出額を差し引くことで、「本来、これくらいの金融資産が残っているはずだ」という理論的な資産額を推計します。
申告された相続財産が、このAIの推計額よりも著しく少ない場合、「申告されていない現金資産(タンス預金)があるのではないか」という強い疑いを持たれ、調査対象としてスコアが高くなるのです。
今から始めるべき相続税対策
では、この強力なAI調査官に対し、私たちはどのように備えれば良いのでしょうか。
まずは相続税の基本と現状を把握する
対策の第一歩は、相続税の基本を正しく知ることです。そもそも、相続税の申告が必要なのは、亡くなった人のうち約9.9%(2023年実績)、およそ10人に1人です。まずはご自身の状況が、申告が必要なケースに該当する可能性があるのかを把握しましょう。
相続税には、課税対象から差し引くことができる「基礎控除」があります。
【相続税の基礎控除額】3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除額となります。相続財産の総額がこの金額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
しかし、問題は「相続財産の総額」を一般の方が正確に把握するのが非常に難しいという点です。預貯金だけでなく、不動産、有価証券、生命保険金、そして先述の名義預金など、すべてを正しく評価し、合算する必要があります。
最も重要な対策は「相続に強い専門家」を選ぶこと
AIによる調査が高度化・複雑化する中で、最も重要かつ確実な対策は「相続税に精通した専門家を味方につけること」です。
しかし、ここで注意が必要です。「税理士なら誰でもいい」というわけでは決してありません。実は、日本の税理士の多くは、相続税の申告実務にほとんど携わったことがないのが実情です。
日本の税理士の数は約8万人ですが、年間の相続税申告件数は約15万件。単純計算で、税理士1人あたり年間2件も扱わない計算になります。実際には、相続専門の事務所に案件が集中するため、ほとんどの税理士は年間1件も経験しないというのが現実です。経験の少ない税理士に依頼してしまうと、財産の評価ミスや特例の見落としなどで、かえって納税額が高くなったり、後々の税務調査で問題を指摘されたりするリスクがあります。
したがって、相続対策を相談する際は、インターネットの広告や宣伝文句を鵜呑みにするのではなく、その税理士が年間に何件の相続税申告を手掛けているのかなど、実績をしっかりと確認し、経験豊富な「相続に強い税理士」を慎重に選ぶことが不可欠です。
まとめ
AI時代の到来により、相続税の税務調査は、性善説に基づいたサンプリング調査から、あらゆるデータを駆使して疑わしい点をピンポイントで指摘する、科学的で網羅的な調査へと大きくシフトします。
意図的な財産隠しはもちろんのこと、知識不足による単純な申告漏れでさえも、もはや許されない時代になったのです。「知らなかった」では済まされません。
相続は、誰にでもいつか必ず訪れる問題です。手遅れになる前に、ご自身の資産状況を正しく把握し、信頼できる専門家とともに、来るべき日に備えておく。それこそが、ご自身と大切なご家族の資産を守るための、最も賢明な資産防衛策と言えるでしょう。
この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。