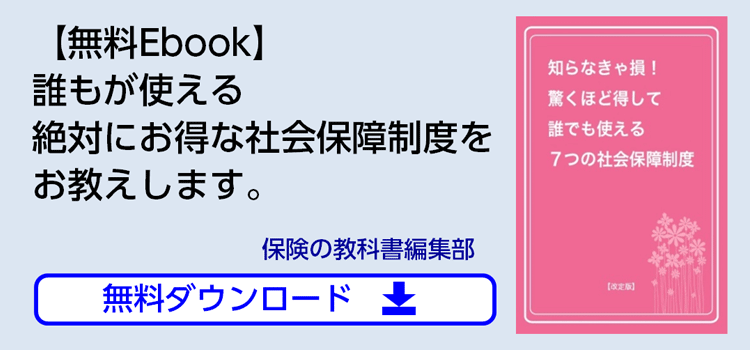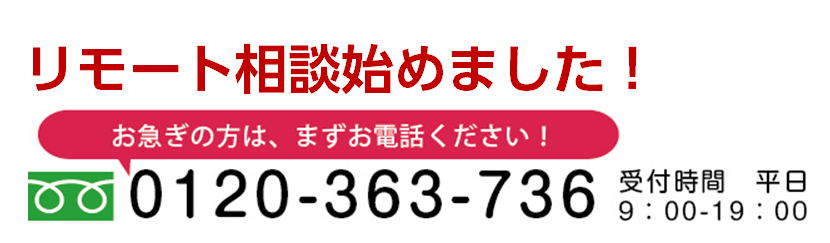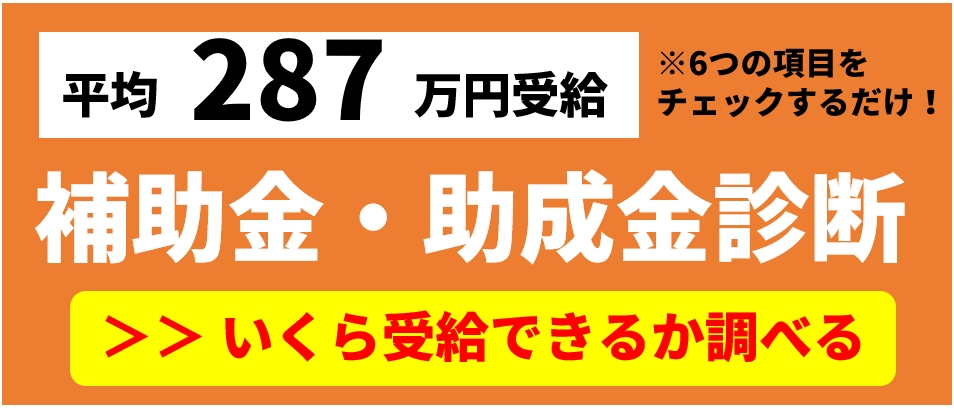遺留分減殺請求を有効に活用するのに必要な5つのポイント
- 2024年7月11日更新

あなたは、遺留分、つまり相続人の最低限の相続分が受け取れなくなっており、そのことについてフォローもしてもらえない状態で、遺留分減殺請求について調べていることと思います。
遺留分減殺請求権は、遺留分が受け取れない場合、つまり遺留分の全部または一部が他の人に行ってしまっている場合に、その人から遺留分の不足分を取り返すことができるという強烈な権利です。
相続がうまくいくためには、最低限、相続人の遺留分への配慮がなされていることが欠かせません。
言い換えれば、あなたが遺留分減殺請求権を行使しなければならないような事態は、好ましいものではありません。やむをえず行使しなければならないというのはまさに断腸の思いでしょう。
この記事では、遺留分減殺請求権とはどういうものか、やむを得ず行使する場合にはどうやって行使するのかということにスポットを当ててお伝えします。
なお、「遺留分とは?遺言作成のため絶対に必要な6つのポイント」とあわせてお読みいただけたら幸いです。
資産防衛の教科書編集部
最新記事 by 資産防衛の教科書編集部 (全て見る)
- 航空機のリースの節税の仕組みとメリット・デメリットの全て - 2024年12月12日
- 養老保険で従業員の退職金を準備するメリット・デメリット - 2024年12月10日
- 養老保険の逆ハーフタックスプランは「節税」になるのか? - 2024年11月29日
目次
1.遺留分減殺請求権は遺留分をきっちり確保するための制度
1-1.遺留分は相続人(配偶者、子または親)の最後の命綱
遺留分減殺請求が何なのかを理解するために、まず、遺留分について軽くおさらいをしておきましょう。
遺留分は、相続人に認められる最低限の相続分です。
なお、遺産を遺す人、つまり相続される人を「被相続人」と言います。「相続人」と紛らわしいですが、真逆の意味なので、必ず押えておいてください。
家族は被相続人に経済的に依存していることが多いので、最後の命綱として遺留分が認められているのです。最後の命綱なので、被相続人が遺留分を侵害するような遺言を遺したとしても、その部分は効力が認められません。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人、つまり、配偶者と、子または親です。
兄弟姉妹に遺留分がないのは、兄弟姉妹は被相続人と独立して生計を立てていることが多く、経済的に依存していることが少ないからです。
1-2.遺留分の計算は2段階
遺留分は、「1.全体の遺留分」→「2.各人の遺留分」の順に計算されます。
「1.全体の遺留分」の計算は相続人が誰かによって決まり、原則として相続財産の1/2です。そして、相続人が親しかいない場合だけ1/3です。なぜなら、一般的に親は、被相続人と財布が別のことが多く、経済的に依存する度合いが、配偶者や子よりも低いからです。
そして、全体の遺留分が確定したところで、次に、「2.各人の遺留分」を算出します。「全体の遺留分」を各自の相続分(法定相続分)に応じて分けます

以上、遺留分がどのようなものか、どうやって計算されるか、簡単におさらいしました。
遺留分減殺請求はまさにこの、最後の命綱としての遺留分が侵害されている場合に、それを取り戻すためのものなのです。
これから、遺留分減殺請求について、誰に、どうやって請求するものなのか、そして、その結果どんな効果が発生するのかということについてお伝えします。
2.遺留分減殺請求は相続人だけでなくアカの他人にもできる
あなたが遺留分を侵害された場合に、遺留分減殺請求ができるのは、他の相続人だけではありません。
- 被相続人から「遺贈」を受けた人
- 被相続人から一定の条件をみたす「贈与」を受けた人
も、遺留分減殺請求の対象になりえます。
2-1.被相続人から「遺贈」を受けた人
「遺贈」とは、遺言によって財産を譲ることです。
遺贈は相続人に対してだけでなく、たとえばお孫様とか、アカの他人に対してもできます。
したがって、被相続人が誰かに遺贈をした場合に、それがあなたの遺留分を侵害しているとなると、あなたは、遺贈の相手方に対して遺留分減殺請求をすることができます。
2-2.一定の条件をみたす「贈与」を受けた人
「贈与」(生前贈与)とは、生前に財産を無償で与えることです。
以下のいずれかの条件をみたせば、遺留分減殺請求のターゲットになります。
- 相続開始前1年間にされた贈与
- 相続開始前1年間より前の贈与で、被相続人と贈与の相手方がいずれも、その贈与が遺留分を害することを知っていた場合
3.遺留分減殺請求のやり方は2段階
では、遺留分減殺請求はどのように行われるでしょうか。
以下の2段階に分けて考えます。
- 遺留分減殺請求のターゲット(相手方・財産)を特定する
- 相手方に対して「遺留分減殺請求を行う」という意思を示す
2-1.遺留分減殺請求のターゲット(相手方・財産)を特定する
まず、遺留分減殺請求のターゲットとなる財産を特定します。つまり、「誰が受け取った」「どの財産」が遺留分を侵害してしまっているかということです。
ここで、ターゲット(相手方・財産)となる遺贈や贈与が複数ある場合は、遺留分減殺請求は以下のルールにのっとって行うことになっています。
- 「遺贈」と「贈与」がある場合は「遺贈」→「贈与」の順に減殺する
- 「遺贈」が複数ある場合は価格の割合に応じて減殺する
- 「贈与」が複数ある場合は価格の割合に応じて減殺する
2-2.相手方に対して「遺留分減殺請求を行う」という意思を示す
最後に、遺留分減殺請求権を行使する方法です。
これは、意思表示、つまり「遺留分減殺請求をするぞ」という意思を相手方に示せば良いことになっています。意思表示は裁判の場で行わなくてもよく、明示的でなくても大丈夫です。
たとえば、他の相続人が「遺贈」を受けて、それがあなたの遺留分を侵害している場合を考えてみましょう。
この場合、判例によれば、あなたは、「その遺贈はNGだ!減殺する!」と言わなくても、他の相続人全員に対して、「遺産分割をどうするか話し合って決めましょう」と言えばいい(遺産分割協議の申し入れをすればよい)ということになっています。なぜなら、そうすることで、遺留分減殺請求の意思が暗黙のうちに示されているからです。
4.遺留分減殺請求は非常に強力な「最後の手段」
もし、あなたが遺留分減殺請求をすると、その分を無条件で取り返すことができます。
また、取り返すのが物理的に不可能な場合は、その代わりに損害賠償金を取ることができます。
このように、遺留分減殺請求権がいったん行使されてしまうと、非常に強力な効果が発生することになります。
だからこそ、あくまで最後の手段なのです。
やむを得ず行使するとしても決して気分の良いものではないと思います。
5.遺留分減殺請求の「二の舞」を繰り返さないために今からできること
遺留分減殺請求権は、やむにやまれず行使するものだと思いますし、行使した側も、行使された側も、つらい思いをするものだと思います。
しかし、もしも得られるものがあるとすれば、それは、同じことを繰り返してはならないという教訓と、ご自身の相続にどう生かすかだと思います。
遺留分の侵害があった、遺留分減殺請求をしなければならなかったという原因は何でしょうか。
私が見聞きした多くのケースでは、ご家族の間のコミュニケーション不全が根本的な原因と考えられるのです。それは決して、誰が正しくて誰が悪かった、ということではありません。
家族を思う心のない人などいないと思います。
私も身近で、互いに思いあっていながら、ちょっとしたすれ違いをこじらせたまま、生涯和解できなかった例を見ています。
まだまだ先の話でなかなか実感が湧かないとは思いますが、ご自身の相続の時、残されたご家族が相続争いで苦しまなくて済むよう、仲良く暮らしていけるよう、今から準備できることがあるはずです。
特に、日頃から、ご家族とのコミュニケーションを密にして、何でも話し合える状態にしておくことが大切だと思います。
まとめ
遺留分減殺請求権は、相続人の最低限の相続分である「遺留分」が侵害された場合に登場する強力な権利です。
被相続人が遺言で遺産の分け方を指定したり、誰かに遺産を分けてあげたりしたことによって、あなたの遺留分が侵害されている場合に問題になる権利です。
ただし、不足分の財産を他の人から取り上げてしまうことができるという強烈な効果があります。
遺留分減殺請求権が行使されるような事態は好ましいものではありません。
ご自身の相続の時になって、このような遺留分減殺請求権が行使されてしまう事態を招かないためには、普段から、ご家族とのコミュニケーションを密にし、また、遺産の分け方について遺言を遺す際に遺留分に配慮する必要があります。
相続税対策・生前贈与の活用をお考えの方へ
【無料Ebook '21年~'22年版】知らなきゃ損!驚くほど得して誰でも使える7つの社会保障制度と、本当に必要な保険

日本では、民間保険に入らなくても、以下のように、かなり手厚い保障を受け取ることができます。
- ・自分に万が一のことがあった時に遺族が毎月約13万円を受け取れる。
- ・仕事を続けられなくなった時に毎月約10万円を受け取れる。
- ・出産の時に42万円の一時金を受け取れる。
- ・医療費控除で税金を最大200万円節約できる。
- ・病気の治療費を半分以下にすることができる。
- ・介護費用を1/10にすることができる。
多くの人が、こうした社会保障制度を知らずに民間保険に入ってしまい、 気付かないうちに大きく損をしています。
そこで、無料EBookで、誰もが使える絶対にお得な社会保障制度をお教えします。
ぜひダウンロードして、今後の生活にお役立てください。
関連記事
-

家族間売買に潜む「みなし贈与」の罠とは?適正価格の算出と贈与税リスクを回避する資産防衛術
親から子へ、あるいは知人間で、不動産や高価な資産を譲り渡す際、「家族なんだから安く譲ってあげたい」「友人価格で安く売ってあげよう」と考えるのは、人情として極めて自然なことです。 しかし、税務の世界においては、この「良かれと思って安くする」行為が、思わ
-

相続税が払えず自己破産?滞納が急増する理由と回避するための生前対策
「相続」は、誰の身にも起こりうる、人生の重要な節目です。 親から大切な財産を受け継ぐ一方で、多くの人が直面するのが「相続税」の問題です。 近年、この相続税を納付できずに「滞納」してしまうケースが年々増加しており、その額は年間400億円を超え、過去最高を更新
-

小規模宅地等の特例|相続税評価額を最大80%抑える活用のポイント
相続する土地の評価額が高い場合、相続税も高額となり、相続人に大きな負担となることがあります。 特に都心部など地価価格が高額な地域にお住まいの方の場合、自宅の土地建物に多額の相続税が発生し、大きな負担になることも考えられます。 しかし、「小規模宅地等の特
-

事業承継の税金対策|オペレーティングリースで自社株評価を下げる方法
長年かけて大切に育て上げてきた会社を、いずれは後継者である子どもに引き継いでほしい。そう願うオーナー経営者にとって、避けては通れない大きな壁が、事業承継に伴う「税金」の問題です。 特に、業績が好調で、内部留保が厚い優良企業であるほど、会社の価値、すな
-

あなたは、相続税の負担を軽くするための制度の一つとして、「基礎控除」の枠の活用を考えていることと思います。 基礎控除の枠は、基本的には法律で固まっているもので、あなたの意思で増減できないものです。なので、その範囲をはっきりさせておくことは、相続税対策
-

相続税の税務調査にAI導入|申告漏れが見抜かれる仕組みと私たちにできる対策
「うちにはそんなに財産はないから、相続税は関係ない」「現金で少しずつ贈与しておけば、税務署には分からないだろう」もし、あなたがそのようにお考えであれば、その認識はもはや通用しない時代になったことを知っておく必要があります。相続税の税務調査にAI(人工知能)
-

不動産売却・相続の節税対策|3,000万円控除と小規模宅地等の特例を解説
不動産は、人生で最も大きな買い物であると同時に、売却や相続の際には、最も大きな税負担を生む可能性のある資産でもあります。 「家を売却したら、思っていた以上に税金がかかって手取りが減ってしまった」 「実家を相続したら、相続税が払えなくて困った」
-

あなたは、ご自身に万一のことがあった場合の相続の際の遺産の分け方をどうしようかとお考えになって、「寄与分」についてお調べになっていることと思います。 寄与分は、言ってみれば、ご家族の中に、あなたの事業の成功に貢献した方とか、あなたの病気療養や介護の世
-

相続税の追徴課税が急増中!国税AIに見抜かれる「申告漏れ」の真実と対策
「自分にはまだ早い」「うちはそんなに資産がないから大丈夫」相続税について、そのように考えてはいませんか?しかし、国税庁の発表によると、相続税の税務調査が行われた案件のうち、なんと85%以上で申告漏れなどの不備が指摘され、追徴課税が発生しています。 こ
-

不動産小口信託受益権を活用し相続対策と資産運用を同時に行う方法
相続または生前贈与においては、現金そのままの形よりも不動産にした方が、相続税・贈与税の負担は抑えられます。 中でも「不動産小口信託受益権」のスキームを利用することで、不動産収入を得ながら、同時に相続税の節税を行うことが可能です。また、小口化して分割し