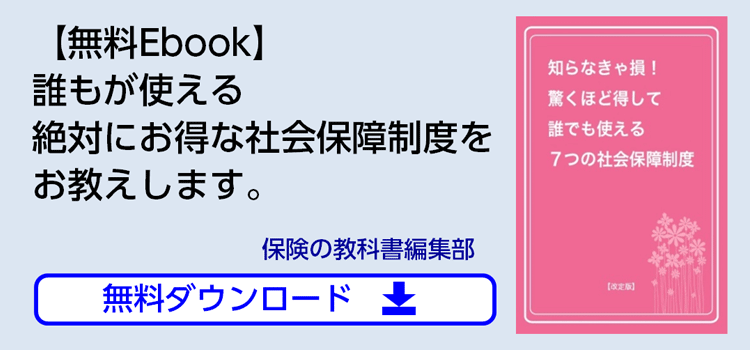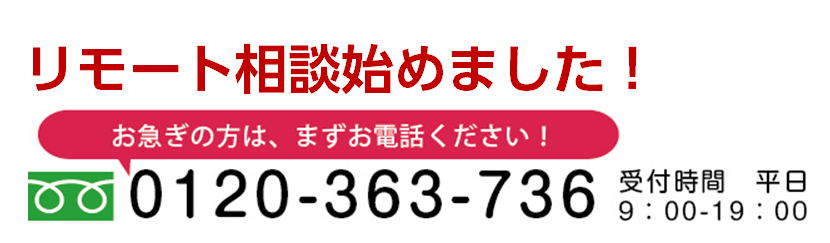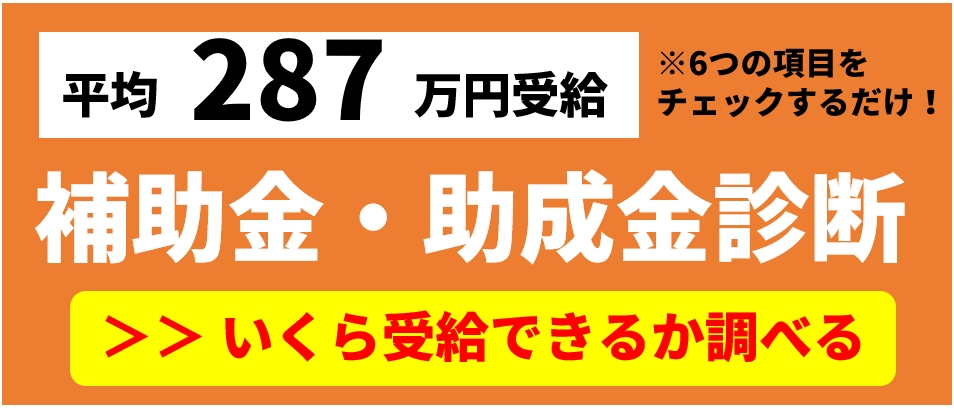相続税対策になり孫の教育資金にも役立つ生前贈与5つのポイント
- 2021年9月7日更新

新学期を控え、お孫さんがいる方は、教育資金としてまとまったお金を出してあげたいとお思いのことと思います。そして、教育資金の生前贈与が相続税対策につながると聞いたことがおありではないでしょうか。
実は、子・孫に教育資金を出してあげる趣旨での生前贈与については、一定の条件のもとで相続税法上の優遇措置が受けられることになっているのです。
これは、国の政策として、上の世代が若い世代へと資産の生前贈与をうながすことによって、若い世代の消費活動を刺激し、経済の発展につなげようという方向性の一環です。
ただし、注意すべき点もあります。
この記事では、孫に充実した教育が受けられるようまとまった額の生前贈与を行うことで、贈与税、ひいては相続税の節税になる制度について説明します。
資産防衛の教科書編集部
最新記事 by 資産防衛の教科書編集部 (全て見る)
- 航空機のリースの節税の仕組みとメリット・デメリットの全て - 2024年12月12日
- 養老保険で従業員の退職金を準備するメリット・デメリット - 2024年12月10日
- 養老保険の逆ハーフタックスプランは「節税」になるのか? - 2024年11月29日
目次
はじめに|教育資金のための贈与は1,500万円まで非課税にできる
あなたが30歳未満の子・孫に教育資金に充ててもらう目的でお金を一括して贈与した場合、条件をみたせば、1,500万円までは贈与税が非課税になります。これは平成31年3月31日までの間の贈与に適用されます。
この非課税の制度は、贈与税の基礎控除(暦年贈与)の年110万円の枠とは完全に別々の制度なので、基礎控除の枠と別口で優遇措置が受けられるというわけです。
贈与税の基礎控除(暦年贈与)については詳しくは「暦年贈与で相続税を減らすのに絶対に押さえたい3つのこと」をお読みください。
また、通常は、あなたが死亡する前の直近3年間に贈与した財産は相続財産に含まれますが、教育資金のための贈与したお金は含まれません。
その結果、贈与税の節税になります。そして、贈与した分について相続財産が減るので、結果的に相続税の節税にもなるのです。
ただし、単に教育資金を孫に贈与しただけではダメで、以下の5つのポイントを押さえておく必要があります。
- 贈与したお金について「教育資金管理契約」を結ぶこと
- 決められた用途のために支出すること
- 贈与の後の払い戻しは認められない
- 領収書等、支払を証明するものが必要
- 子・孫が30歳になった時点で使い切れなかった額に贈与税がかかる
これから、それぞれについて説明していきます。
ポイント1. 贈与したお金について「教育資金管理契約」を結ぶこと
まず、贈与するだけでなく、贈与したお金について金融機関等との間で「教育資金管理契約」を結ぶことが必要です。具体的には以下のいずれかです。
- 子・孫が受け取ったお金について、銀行等と「教育資金管理契約」を結び、預け入れる場合
- 子・孫のために信託会社と「教育資金管理契約」を結んでお金を信託し、子・孫が「信託受益権」を得る場合
- 子・孫が受け取ったお金について、証券会社と「教育資金管理契約」を結び、証券会社の営業所等において有価証券を購入する場合
いずれにしても、子・孫にお金をポンとあげるだけでは足りず、金融機関等との「教育資金管理契約」が必要というわけです。
ポイント2. 決められた用途のために支出すること
「学校」等のためなら1,500万円まで使える
学校等の正規の教育機関のための費用は、1,500万円の枠いっぱいまで使ってよいことになっています。学校等は公立・私立を問いません。また、保育園・幼稚園、小学校、中学校、高校、大学はもちろん、専門学校や職業訓練校等、一切の学校が含まれます。
認められている支出目的は、以下の通りです。
- 入学金・授業料、入園料・保育料、施設設備費
- 入学試験・入園試験の受験料
- 在学証明・成績証明等の手数料
- 学用品の購入費・修学旅行費・学校給食費その他必要な費用
「学校」等以外のために500万円まで振り分けられる
正規の教育機関ではない学習塾や、習い事等の費用はどうでしょうか。
この場合は、1,500万円の枠のうち500万円まで振り分けてよいことになっています。
認められている支出目的は、以下の通りです。
- 習い事(学習塾、サッカー教室、ピアノ教室その他)の月謝
- 習い事の教室・指導者を介して購入した物品の代金
- 習い事のための施設使用料
- 通学定期代
- 海外留学のための引越しに伴う渡航費
- 国内の遠方の学校への進学のための引越しに伴う交通費
ポイント3. 贈与の後の払い戻しは認められない
贈与とは所有権自体を与えてしまうものなので、当然と言えば当然ですが、贈与の後に金融機関等に対して「やはり経済状態が苦しいので払い戻ししたい」ということはできません。
したがって、無理のない範囲で贈与を行う必要があります。
ポイント4. 領収書等、支払を証明するものが必要
贈与税の非課税の特例は、あくまでも、贈与されたお金が教育資金として使われることが前提です。したがって、領収証等、支払を証明するものをとっておき、金融機関等に提出しなければなりません。
ポイント5. 孫が30歳になった時点で使い切れなかった額に贈与税がかかる
贈与税の非課税の特例は、孫が全ての額を教育資金として使うことが前提です。
孫が30歳になるまでの間に使い切れなかった場合、余った金額については、贈与税の非課税の趣旨があてはまりません。そのため、孫が30歳になった時点で余った金額に贈与税が課税されることになります。
まとめ
子・孫のため教育資金を一括贈与する場合の贈与税の非課税の特例を活用した相続税対策について、5つのポイントをお伝えしてきました。
単に贈与すれば良いのではなく、教育資金としての活用を前提としたルールがあることがお分かりいただけたことと思います。ただし、そのルールは決して難しいものではありません。
また、あなたご自身の節税だけでなく、子・孫に充実した教育を与えることで幸せな人生を送るサポートができるという魅力的な制度です。
この記事をお読みになった上で、上手に活用していただければと思います。
相続税対策・生前贈与の活用をお考えの方へ
【無料Ebook '21年~'22年版】知らなきゃ損!驚くほど得して誰でも使える7つの社会保障制度と、本当に必要な保険

日本では、民間保険に入らなくても、以下のように、かなり手厚い保障を受け取ることができます。
- ・自分に万が一のことがあった時に遺族が毎月約13万円を受け取れる。
- ・仕事を続けられなくなった時に毎月約10万円を受け取れる。
- ・出産の時に42万円の一時金を受け取れる。
- ・医療費控除で税金を最大200万円節約できる。
- ・病気の治療費を半分以下にすることができる。
- ・介護費用を1/10にすることができる。
多くの人が、こうした社会保障制度を知らずに民間保険に入ってしまい、 気付かないうちに大きく損をしています。
そこで、無料EBookで、誰もが使える絶対にお得な社会保障制度をお教えします。
ぜひダウンロードして、今後の生活にお役立てください。
関連記事
-

家族間売買に潜む「みなし贈与」の罠とは?適正価格の算出と贈与税リスクを回避する資産防衛術
親から子へ、あるいは知人間で、不動産や高価な資産を譲り渡す際、「家族なんだから安く譲ってあげたい」「友人価格で安く売ってあげよう」と考えるのは、人情として極めて自然なことです。 しかし、税務の世界においては、この「良かれと思って安くする」行為が、思わ
-

相続税の税務調査にAI導入|申告漏れが見抜かれる仕組みと私たちにできる対策
「うちにはそんなに財産はないから、相続税は関係ない」「現金で少しずつ贈与しておけば、税務署には分からないだろう」もし、あなたがそのようにお考えであれば、その認識はもはや通用しない時代になったことを知っておく必要があります。相続税の税務調査にAI(人工知能)
-

不動産小口信託受益権を活用し相続対策と資産運用を同時に行う方法
相続または生前贈与においては、現金そのままの形よりも不動産にした方が、相続税・贈与税の負担は抑えられます。 中でも「不動産小口信託受益権」のスキームを利用することで、不動産収入を得ながら、同時に相続税の節税を行うことが可能です。また、小口化して分割し
-

不動産売却・相続の節税対策|3,000万円控除と小規模宅地等の特例を解説
不動産は、人生で最も大きな買い物であると同時に、売却や相続の際には、最も大きな税負担を生む可能性のある資産でもあります。 「家を売却したら、思っていた以上に税金がかかって手取りが減ってしまった」 「実家を相続したら、相続税が払えなくて困った」
-

小規模宅地等の特例|相続税評価額を最大80%抑える活用のポイント
相続する土地の評価額が高い場合、相続税も高額となり、相続人に大きな負担となることがあります。 特に都心部など地価価格が高額な地域にお住まいの方の場合、自宅の土地建物に多額の相続税が発生し、大きな負担になることも考えられます。 しかし、「小規模宅地等の特
-

相続税の追徴課税が急増中!国税AIに見抜かれる「申告漏れ」の真実と対策
「自分にはまだ早い」「うちはそんなに資産がないから大丈夫」相続税について、そのように考えてはいませんか?しかし、国税庁の発表によると、相続税の税務調査が行われた案件のうち、なんと85%以上で申告漏れなどの不備が指摘され、追徴課税が発生しています。 こ
-

相続税が払えず自己破産?滞納が急増する理由と回避するための生前対策
「相続」は、誰の身にも起こりうる、人生の重要な節目です。 親から大切な財産を受け継ぐ一方で、多くの人が直面するのが「相続税」の問題です。 近年、この相続税を納付できずに「滞納」してしまうケースが年々増加しており、その額は年間400億円を超え、過去最高を更新
-

事業承継の税金対策|オペレーティングリースで自社株評価を下げる方法
長年かけて大切に育て上げてきた会社を、いずれは後継者である子どもに引き継いでほしい。そう願うオーナー経営者にとって、避けては通れない大きな壁が、事業承継に伴う「税金」の問題です。 特に、業績が好調で、内部留保が厚い優良企業であるほど、会社の価値、すな
-

あなたは、ご自身に万一のことがあった場合の相続の際の遺産の分け方をどうしようかとお考えになって、「寄与分」についてお調べになっていることと思います。 寄与分は、言ってみれば、ご家族の中に、あなたの事業の成功に貢献した方とか、あなたの病気療養や介護の世
-

あなたは、相続税の負担を軽くするための制度の一つとして、「基礎控除」の枠の活用を考えていることと思います。 基礎控除の枠は、基本的には法律で固まっているもので、あなたの意思で増減できないものです。なので、その範囲をはっきりさせておくことは、相続税対策