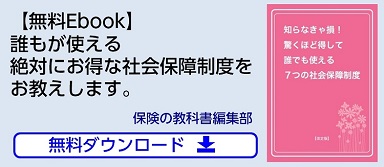「うちの会社にも、いつか税務調査が来るのだろうか…」これは、事業を営むすべての経営者が、心のどこかで抱いている不安ではないでしょうか。日頃から適正な申告と納税を心がけているにもかかわらず、ある日突然、税務署から連絡が来る可能性は、残念ながらゼロではありません。
しかし、税務調査は、決して無作為に行われているわけではありません。税務署は、国税総合管理システム(KSKシステム)という巨大なデータベースを活用し、膨大な申告データの中から、申告内容に異常値や疑問点がある、つまり「税務上のリスクが高い」と判断される会社を、優先的に調査対象として選定しています。
裏を返せば、日頃から「税務リスクが低い」と評価されるような、健全な経理・財務体制を構築しておくことが、税務調査の確率を大幅に引き下げるための、最も効果的な対策となるのです。この記事では、どのような会社が税務調査の対象として選ばれにくいのか、その共通する5つの特徴を、具体的な経営管理の視点から詳しく解説していきます。
The following two tabs change content below.
1.税務調査はどのように選定されるのか?
税務調査の対象選定は、調査官の勘や経験だけに頼っているわけではありません。その中心にあるのが、前述のKSKシステムです。このシステムは、全国の法人の申告データを一元管理し、過去数年間の業績推移や、同業他社との比較分析などを自動的に行います。
この分析過程で、
- 売上や利益の急激な変動
- 特定の経費の異常な増加
- 業界平均から大きく乖離した利益率
といった、「異常値」や「特異点」が検出された場合に、その会社は調査対象候補としてリストアップされるのです。つまり、税務調査を避けるための基本は、このシステムに「異常」と判定されないような、安定し、かつ、合理的な申告内容を維持することにあります。
2.税務調査のリスクが低い会社に共通する5つの特徴
それでは、具体的にどのような特徴を持つ会社が、税務調査のリスクが低いと判断されやすいのでしょうか。そのポイントを5つに分けて見ていきましょう。
①専門家による品質の高い申告書
申告書は、会社の顔です。その第一印象は、調査官がその会社に対して抱く心証を大きく左右します。会計帳簿と決算書、申告書の数字が完璧に整合しており、記載内容も明瞭で、論理的に整然と作成されている申告書は、「この会社は、経理体制がしっかりしている」という無言のメッセージを発します。
特に、その信頼性を客観的に証明する上で極めて有効なのが「書面添付制度」の活用です。これは、顧問税理士が、その申告書を作成するにあたり、「どのような資料を、どの程度確認し、どのような事項について相談を受けたか」などを詳細に記載した書面を、申告書に添付する制度です。この書面が添付されている場合、税務署は、調査の必要性を感じても、まず税理士に意見を聴取する機会を設けなければなりません。
税理士による品質保証がなされている、という客観的な事実が、申告書の信頼性を格段に高め、調査へのハードルを上げる効果があるのです。
②健全で保守的な会計処理
税務調査の主な目的は、申告漏れや所得隠し、つまり「過少に申告された所得」を見つけ出し、追加で税金を徴収することです。しかし、世の中には、金融機関からの融資などを有利に進めるために、意図的に利益を多く見せかける「粉飾決算」を行っている会社も存在します。
もし、このような利益を過大に計上している会社に税務調査が入った場合、調査官は架空売上などを指摘し、正しい利益を計算し直すことになります。その結果、会社の利益は減少し、納めるべき税金も少なくなります。つまり、税務署は、払い過ぎていた税金を会社に返還(還付)しなければならなくなるのです。
追徴課税という「成果」を求める税務調査において、還付で終わる可能性のある調査は、優先順位が低くなります。日頃から、過度な利益計上を避け、健全で保守的な会計処理を心がけることが、結果として調査リスクを遠ざけることに繋がります。
③業績の安定性と継続性
税務署が申告書を分析する際、特に注目するのが「変化」や「異常値」です。長年にわたり、売上や利益、各種経費の割合が、大きな変動なく安定して推移している会社は、経営が堅実で、経理処理も一貫している可能性が高いと判断されます。
逆に、特定の事業年度だけ、売上や利益が不自然に急増(または急減)していたり、毎年、利益率が大きく変動していたりする会社は、「その変動の理由は何か?」「何か特別な取引や、通常と異なる会計処理があったのではないか?」という疑念を抱かれやすくなります。もちろん、事業には浮き沈みがつきものです。重要なのは、もし業績に大きな変動があった場合には、その理由を後述する「事業概況説明書」などで、自ら積極的に説明しておくことです。
④業界平均から乖離しない財務指標
税務署は、長年の調査データの蓄積により、業種ごとの平均的な売上総利益率(粗利率)や、売上に対する主要な経費(人件費、外注費など)の割合といった、膨大な統計データを保有しています。そして、提出された申告書を、これらの「業界平均値」と比較し、異常がないかをチェックしています。
例えば、飲食店の平均的な原価率が30%程度であるのに対し、ある飲食店の申告書で原価率が50%と異常に高くなっている場合、「架空の仕入れを計上して、利益を圧縮しているのではないか?」という疑念が生じます。このように、業界の平均値から大きく逸脱した財務指標は、税務調査のきっかけとなりやすいのです。自社の決算数値が、業界の標準的な範囲内に収まっていることは、調査リスクが低いことの一つの証左となります。
⑤明確で追跡可能な取引記録
これは、特にBtoCの現金商売を営む事業者にとって重要な視点です。税務調査は、限られた日数で、申告の誤りを見つけ出す、効率性が求められる業務です。そのため、取引先が限定され、一つひとつの取引記録が契約書や請求書で明確に裏付けられるBtoB事業に比べ、不特定多数の顧客との少額な現金取引が繰り返されるBtoC事業(飲食店、小売店など)は、調査に多大な手間と時間がかかります。
だからといって、現金商売の調査が手薄になるわけではありません。むしろ、売上除外などの不正が行われやすい業種として、常に監視されています。ここで重要になるのが、日々の取引記録を、いかに明確で、追跡可能な形で残しているか、ということです。最新のPOSレジシステムを導入し、すべての売上を正確に記録している、現金管理を徹底している、といった体制が整っていれば、調査官も「この会社から大きな不正を見つけ出すのは難しい」と判断する可能性が高まります。
3.税務調査リスクを能動的に下げるための具体的なアクション
異常値は、申告書で自ら説明する
もし、不動産の売却や保険金の受け取りなど、その期だけの特別な理由で、利益が一時的に急増した場合は、その旨を申告書に添付する「事業概況説明書」に、具体的に記載しておくことが極めて有効です。「当期は、〇〇の理由により、一時的に利益が増加しています」と、あらかじめ正直に説明しておくことで、税務署側の不要な疑念を払拭し、調査対象に選定されるリスクを、大きく引き下げることができます。
まとめ
税務調査のリスクを低減するための秘訣は、何か特別な裏技にあるわけではありません。それは、日々の経営活動の中にこそ存在します。
- ①専門家と連携し、品質の高い、透明性のある申告書を作成する。
- ②利益を過大に見せることなく、健全で保守的な会計処理を貫く。
- ③安定した業績を維持し、もし大きな変動があれば、その理由を明確に説明する。
- ④自社の財務指標が、業界の標準から大きく外れていないか、常に意識する。
- ⑤すべての取引について、明確で追跡可能な記録を残す体制を構築する。
これらの特徴を持つ会社は、税務署の視点から見れば、「調査をしても、大きな成果が期待できそうにない、税務リスクの低い会社」と映ります。税務調査を過度に恐れるのではなく、調査官がどのような視点で会社を見ているかを理解し、自社の経理・財務体制を、常に見直していくこと。それこそが、経営者が実践できる、最も効果的で、かつ本質的な税務調査対策と言えるでしょう。
この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。