次のようなことでお悩みではありませんか?
・自分にピッタリの保険を選んで加入したい
・現在加入中の保険の内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
・どんな保険に加入すればいいのか分からない
もしも、保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
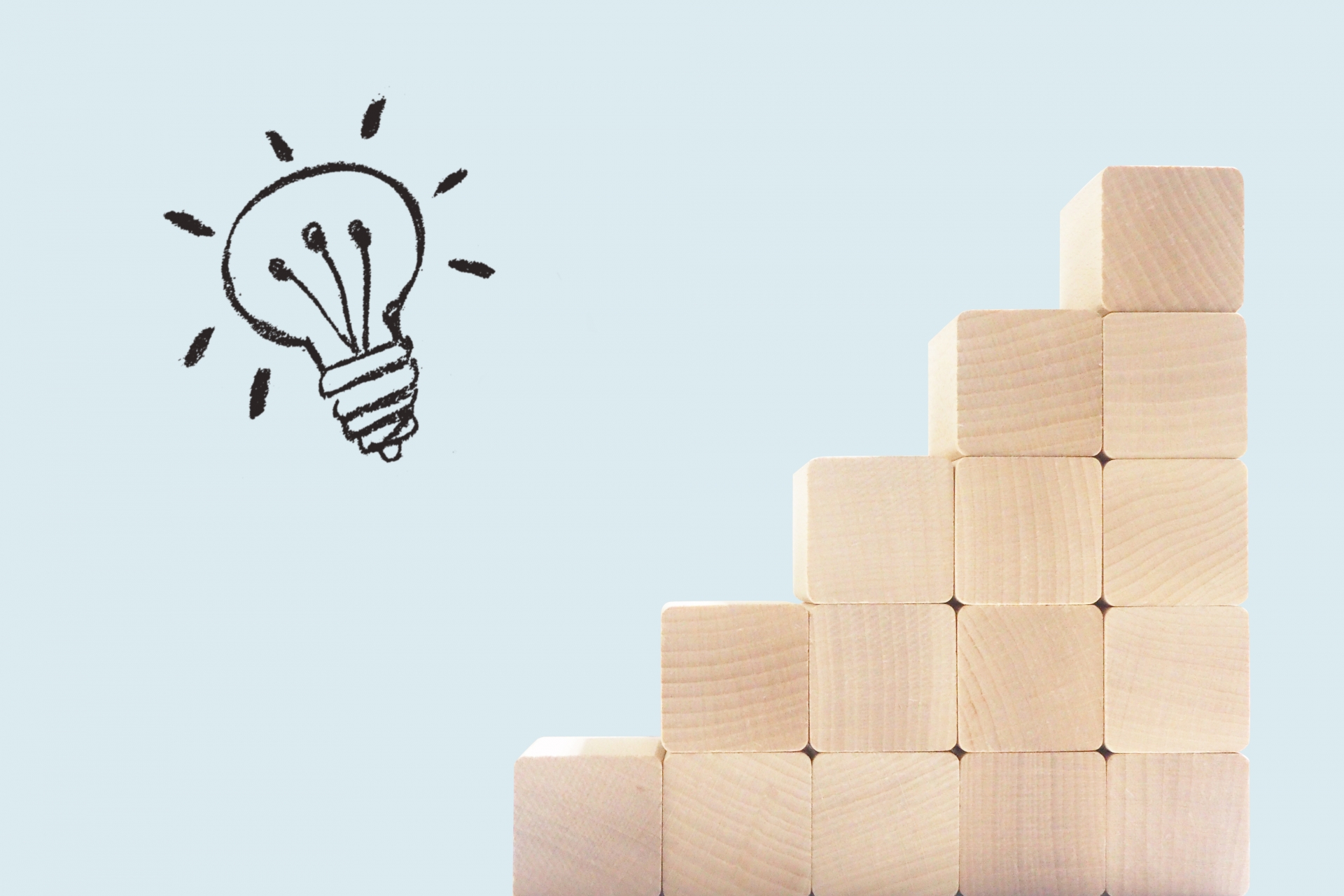
保険料が掛け捨てにならないのが魅力の貯蓄型の生命保険ですが、一方で保険料が高い側面もあり、どういう場合に契約すればよいか迷っていませんか?
ここでは、貯蓄型の生命保険の2つの役割と、さらに貯蓄性を高める2つの方法を解説します。
この記事は、あなたが掛け捨てもしくは貯蓄性のある生命保険のどちらを選ぶべきか判断する際の参考になります。
資産防衛の教科書編集部
最新記事 by 資産防衛の教科書編集部 (全て見る)
目次
貯蓄型の生命保険は、契約者が亡くなった際に保険金が受け取れる点は、掛け捨て型の生命保険と同じです。
その一方で毎月の保険料が積み立てられ、解約時や満期時のいずれかに必ずお金を受け取れる点が掛け捨て型との違いです。
このようにお金を貯めることができるため、貯蓄型の生命保険と呼ばれます。
貯蓄型の生命保険には終身保険・養老保険の2種類があり、戻ってくるお金の額に大きな違いがあります。
いずれも、このところのマイナス金利の影響によって貯蓄の効率が悪くなってしまいました。
けれど終身保険の方は、選び方や契約方法によってはお金を増やすことができ貯蓄としての価値があります。
たいする養老保険は、結論から言って支払ったお金より返ってくるお金の方が少ないことがほとんどなので、貯蓄としてはおすすめできません。
結論から言うと、死亡保障を重視して生命保険を選ぶのであれば、掛け捨て型と比べて貯蓄型は格段に割高となりむいておりません。
保険料がおさえられる掛け捨て型をおすすめします。
実際、どの程度違うか、A生命の保険商品を例にとって比較してみましょう。
終身保険・掛け捨て型(定期保険)いずれも30歳男性が1,000万円の死亡保障をつけて加入するものとします。
また掛け捨て型の保険満了の年齢を60歳、終身保険の保険料払込満了も60歳に設定します。この場合の保険料は以下の通りです。
ご覧の通り、60歳までの間であれば、同じ1,000万円の保障をつけるのに貯蓄型の方が約9倍も高くなっています。
掛け捨て型なら貯蓄型よりはるかに低い保険料で、同じ額もしくはさらに高い額の死亡保障を用意することが可能です。
終身保険では死亡保障・貯蓄という2つの側面があることは書きました。
また、上で書いた通り、死亡保障を優先する場合、掛け捨て型の方が適しています。
それでは貯蓄型の生命保険である終身保険は、どういった目的で利用するのが適しているのか、1つずつ見ていきましょう。
生命保険における死亡保障は、主に以下2つの目的で契約されます。
このうち、遺された家族の生活費として死亡保障を用意するのに適しているのは、掛け捨て型の生命保険です。
上で比較したように、少ない保険料で多くの保険金を用意することができるためです。
例えば稼ぎ手である一家のお父様が亡くられた場合、まとまった金額の保険金を遺す必要があります。
その場合でも、掛け捨て型なら保険料をおさえることが可能です。
また仮に掛け捨て型で契約を60歳満了とした場合でも、その頃には子供も自立していると考えられ死亡保障の必要性が少なくなります。
これも掛け捨て型が適している理由です。
一方、貯蓄型の生命保険は、整理費用として利用するのが適しています。
日本消費者協会の調査によると、葬儀費用の平均は約196万円。地域などによって差がでる可能性はあるものの、少なくとも遺された家族のための生活費より、必要な金額は断然少なくてすみます。
このぐらいであれば、貯蓄型の生命保険でも比較的用意しやすいでしょう。
また終身保険となるので、定期保険ではカバーするのが難しい高齢で亡くなった際にも、保険金が提供され家族の負担を減らせるのも整理費用として適している理由です。
終身保険の貯蓄性は、老後のための資金を貯めるのに活用するのが有効です。
子供が独立するまでは死亡保障として契約を残しておき、子供も独立して定年で退職したあとには、解約して貯まったお金を老後の生活資金として利用します。
この場合、例えば60歳の定年時に払込満了となるよう契約を設計することで、以下の図のように60歳以降に解約した際に、払い込んだ保険料の金額より多くの払戻金を受け取ることができます。
一例としてB生命の終身保険をみてみましょう。
この保険で、死亡時の保険金を1,000万円と設定した場合に、30歳男性が加入して60歳になるまでに払い込む保険料の総額は約780万円(保険料は毎月21,640円)。
たいして60歳払込満了時点で解約すると約860万円が受け取れて、その払戻率は約110%となります。
また60歳時点で老後資金が十分であれば、そのまま契約を残しておくことで、解約したときにもらえるお金をさらに増やすことも可能です。
この貯蓄性を活かして、学資保険の代わりとして利用する方法もあります。
例えば30歳で子供ができた男性が、終身保険に加入すると仮定してシミュレーションしてみましょう。
この男性は自分が45歳となって子供が高校へ上がる段階や48歳となって子供が大学へ上がる段階で、一定の資金が欲しいとします。
そこで先ほどのB生命の終身保険を以下条件で加入します。
この場合、満期となる15年後までに支払う払込保険料累計と15年目の段階で解約した際の解約返戻金は以下の通りです。
銀行に預けておくより利率がよい上に、万が一、契約者の方がこの15年以内に亡くなった場合は500万円の保険金を家族が受け取ることもできます。
また「高校の資金はあるから大学に入るまで貯めておこう」といったように、解約するまでの期間を先延ばしにすれば、以下の通りさらに払戻率がよくなります。
終身保険では契約内容を工夫することで、貯蓄の効率を高めることが可能です。
具体的な方法として以下2つがあげられます。
1つずつ解説します。
上の例に出したように、15年払や10年払のように出来るだけ短い期間で保険料を支払い終えた方が、支払うべき保険料の総額が少なくなる上に払戻の返戻率が高まります。
その分だけ毎月の保険料が高くなりますが、お金に余裕があれば、この方法をとった方がお得です。
またこの方法は、子供の学資保険代わりに終身保険を使いたい際に適しています。
例えばC生命の終身保険において死亡保険金500万円、払込期間を15年払いとし、契約から20年目に解約した場合の払込保険料の累計や解約返戻金は以下の通りです。
終身保険には、「ドル建て」や「変額」というタイプもあります。ここではドル建ての終身保険について簡単に紹介します。
ドル建ての終身保険とは、その名の通り日本円ではなく米ドルなどで支払い、解約返戻金も米ドルなどで受け取るタイプの終身保険のことです。
マイナス金利政策などの影響により、円建てよりもドル建ての終身保険の方が解約時の返戻率が高くなっています。
また、ドル建ての方が保険会社では資金運用で収益が見込めることから保険料が安くなります。
こういった理由から、貯蓄性を高めるのであればドル建ての終身保険という選択肢もあります。
一例としてD生命の米ドル建て終身保険の例をみてみましょう。
1米ドル約110円換算とし、5万米ドル(約550万円)の死亡保険金を用意し、払込期間を10年と短くした場合の例は以下の通りです。
※分かりやすく日本円のみで表示します。
米ドル建ての保険で注意しなければならないのは「為替リスク」です。これは、解約返戻金を受け取る時になっていきなり極端な円高ドル安になった場合に、元本割れを起こす可能性があるというリスクです。
ただし、為替リスクには有効な対処法があります。保険料を月払いにして、その都度、その時の為替相場に応じた金額(円)を支払い続けていくことです。
解約時に突然、払込期間中の為替相場の平均と比べて極端な円高ドル安にならない限り、大きな損失を被ることはありません。
なお、運悪くそのような極端な事態になった場合でも、為替相場が落ち着くまで待つ方法もあります。
貯蓄性の生命保険である終身保険は、亡くなった際の死亡保障と貯蓄という2つの側面があります。
死亡保障という点では、葬儀などの整理費用として活用するのが適しています。
一方の貯蓄という面では、老後の生活資金や学資保険かわりに活用するのが最適です。
また終身保険の貯蓄性を高めるやり方として、できるだけ短期間で支払いを完了し契約をのこしておく方法や、ドル建てのタイプを選ぶ方法などが挙げられます。
次のようなことでお悩みではありませんか?
・自分にピッタリの保険を選んで加入したい
・現在加入中の保険の内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
・どんな保険に加入すればいいのか分からない
もしも、保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

日本では、民間保険に入らなくても、以下のように、かなり手厚い保障を受け取ることができます。
多くの人が、こうした社会保障制度を知らずに民間保険に入ってしまい、 気付かないうちに大きく損をしています。
そこで、無料EBookで、誰もが使える絶対にお得な社会保障制度をお教えします。
ぜひダウンロードして、今後の生活にお役立てください。

利益が出過ぎた社長へ捧ぐ「決算直前の駆け込み節税」ベスト9!無策で高額納税する前に読むべき資産防衛の鉄則
「今期は予想以上に業績が良く、過去最高益になりそうだ」経営者にとって、これほど嬉しいことはありません。しかし、決算月が近づくにつれて、その喜びは「納税への恐怖」へと変わっていきます。日本の法人税率は、実効税率で約30%〜34%です。汗水流して稼いだ利益の3

交際費の「1万円基準」で節税枠が拡大!飲食代を会議費で落とす鉄則
経営者の皆様にとって、取引先との会食やゴルフ、贈答といった「交際費」は、ビジネスを円滑に進め、将来の売上を作るための重要な「投資」です。しかし、その一方で、「どこまでが経費として認められるのか?」「使いすぎると税務調査で否認されるのではないか?」という不安

小規模企業共済で1,670万円の資産形成?高所得な経営者ほど得をする「国の退職金制度」を徹底解説
「小規模企業共済」という言葉を聞いたことはあっても、その具体的なメリットや仕組みを詳しく理解している経営者は意外と少ないのではないでしょうか。「なんとなく節税になりそうだけど、資金が拘束されるのはちょっと…」と、加入を先送りにしている方もいるかもしれません

役員賞与は最低150万円以上出すべき?ボーナス活用で税金と社会保険料をダブルで削減する裏ワザ
「今期は予想以上に利益が出そうだ。税金で持っていかれるくらいなら、役員賞与を出して節税したい」そう考える経営者の方は多いでしょう。しかし、「役員賞与は経費にならない」という原則があるため、二の足を踏んでいる方もいらっしゃるかもしれません。 実は、ある

固定資産税ゼロで最短4年償却!「トレーラーハウス」が優秀な節税投資と呼ばれる理由
不動産投資を検討する際、多くの経営者が直面するのが「固定資産税」や「長い減価償却期間」という壁です。アパートやマンションへの投資は、長期的に安定した収益が見込める一方で、毎年の固定資産税負担が重く、また建物の減価償却期間が長いため(木造で22年、RC造で4

「これは経費で落ちる?」経営者が知っておくべきグレーゾーン支出20連発
会社経営において、「節税」は利益を最大化するための重要な戦略です。「可能な限り経費として計上し、法人税を抑えたい」経営者なら誰もがそう願うはずです。しかし、その一方で、「この領収書は本当に経費にして大丈夫なのか?」という不安が常につきまといます。 も

高所得なサラリーマンこそ実践すべき「最強の節税対策」9選!手取りを確実に増やす資産防衛術
「年収は1,000万円を超えているはずなのに、なぜか生活に余裕がない」「昇給して額面は増えたけれど、手取り額がほとんど変わっていない気がする」 高所得者の方であれば、一度はこのような虚しさや違和感を覚えたことがあるのではないでしょうか。日本の税制は、

役員借入金は「社長の第二の財布」?メリットと放置の危険性を徹底解説
会社経営をしていると、急な資金需要に対応するため、社長個人のポケットマネーを一時的に会社に入れたり、会社の経費を立て替えたりすることは、珍しいことではありません。金融機関の融資審査を待つことなく、スピーディーに資金を調達できるこの方法は、一見すると非常に便

合法的に利益を「無税」で貯蓄せよ!会社を救う最強の「簿外資産」スキーム7選を税理士が完全解説
「今期は過去最高益が出そうだ。しかし、このままでは法人税でキャッシュがごっそり減ってしまう…」「来期以降の不況に備えて、内部留保を厚くしたいが、税金を払った後では資金が貯まらない」 経営者にとって、利益が出ることは最大の喜びであると同時に、納税による

法人名義での投資信託|個人とは違う5つのメリットと注意点を解説
新NISA制度の開始などをきっかけに、個人の資産運用への関心が急速に高まっています。その中でも「投資信託」は、専門家が運用を行う手軽さから、多くの方が活用している金融商品です。では、この投資信託を、個人としてではなく、会社(法人)として運用することに、どの