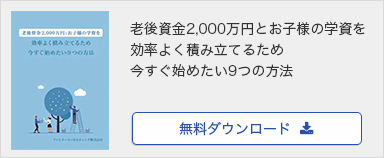勤め上げた会社員が退職する際に、御礼の意味も込めて支給する退職金。
受け取る側にとっては、これからの生活を支える重要なお金になります。
そんな退職金を支給する経営者側としては、いくら支払えばいいのか気にあるところです。
勤続年数によっても変わってきますし、役職などによっても当然額に変化があるでしょう。
どのような場合にどのくらいの退職金を出せばいいのか、経営者なら気になりますよね。
今回はそんな退職金の相場について、中小企業に絞ってみていきます。
中小企業の経営者の方は、是非参考にしてみてください。
The following two tabs change content below.
私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。
1.中小企業の退職金の相場について
まず、中小企業ではどの程度の金額を退職金として見据えているのでしょうか。
東京都産業労働局の平成30年度の調査によると、退職金制度を設けている企業が全体の71.3%、その中の75.9%が「退職一時金のみ」と回答しています。
つまり、全体の50%ほどが退職一時金として、退職金を支給しているということです。
また、退職金の支払い準備については、退職金制度を設けている企業の64.4%が「社内準備」で準備しており、次いで「中小企業退職金共済制度」で準備しているという企業が48.5%となっています(複数回答)。
参考:「中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)」(東京都産業労働局HP)
1.1.退職金の値段について
退職金の値段の算出方法については、「退職金算定基礎額×支給率」という方式をとっている企業が多く、退職金を支給している企業の内44%が採用しています。
「勤務年数に応じた一定額」で退職金を支給している企業も多く、全体の21.5%ほどです。
「退職金算定基礎額」の算出方法も企業によって違いますが、ほとんどの企業が、退職時の基本給やそれに一定率をかけた数値に、勤続年数をかけたものを利用しています。
1.2.退職金支給の最低勤続年数について
退職金を支給するための最低勤続年数は、退職理由が会社都合、自己都合どちらの場合でも「3年」という企業が最も多く、ついで「1年」から退職金を出すという企業も多いです。
1年目から退職金を出すという企業が多いのは意外ですね。
転職によって雇用者側が自由な働き方を求めるようになった時流に合わせていると考えられます。
1.3.退職一時金の特別加算制度について
役職や功労による退職金の特別加算制度を採用している企業もあり、退職金を出す企業の内、37.4%が採用しています。
上記制度を採用している企業の場合、功労による加算制度を設けている所が多く、80.2%が採用しています。次点は「業務上死傷病」で、20.1%です。
役職等も含め功労として加算していき、総合的に評価する企業が多いということですね。
こういった制度等を活用し、企業ごとの退職金を算出しているわけです。
2.勤続年数別の退職金相場について
次に、勤続年数別の退職金の相場について見ていきましょう。
高卒・大卒の勤続年数別の退職金相場は以下の通りです。
高卒の場合

大卒の場合

3.業種別の退職金相場
続いて、業種別の退職金相場を見ていきましょう。
大卒で満勤勤続した場合の、業種別の退職金相場は以下の通りです。

銀行の相場が低いのが意外ですね。
4.退職金の積立方法について
ここまで退職金の相場について様々な視点で見てきましたが、経営者が退職金の金額と同じく気になるのが、退職金の積立方法でしょう。
ここでは企業が行える退職金の積み立て方法について、簡単に説明していきます。
4.1.中小企業退職金共済
中小企業であれば、中小企業退職金共済を利用することできます。
中小企業退職金共済は国が運営している制度で、中小企業が従業員一人ひとりのために毎月掛金を支払って、退職金を積み立ててあげるものです。
2018年12月末時点で、加入企業数は368,881所、加入従業員数は3,469,911人にのぼっています。
中小企業退職金共済を使えば、掛金の管理や運用、退職金支払いの手続きまで中小企業共済本部が代行してくれるため、加入企業に手間がかからないのが特徴です。
詳しくは「中小企業退職金共済で従業員の退職金を積み立てるメリットと注意点」をご覧ください。
4.2.養老保険の福利厚生プラン
養老保険は、契約期間中に保険の対象者(被保険者)が亡くなった場合は死亡保険金が支払われ、何事もなく契約期間が満了した場合は満期保険金が支払われる保険です。
退職金を積み立てるのに利用されるのは、「福利厚生プラン」というもので、一定の条件をみたす従業員全員が加入することで、保険料の1/2を損金に算入できるという特徴があります。
詳しくは「養老保険で従業員の退職金を準備するメリット・デメリット」をご覧ください。
まとめ
ここまで中小企業退職金の退職金相場についてお話ししていました。
退職金制度は中小企業の7割以上が採用しており、メジャーな制度です。
勤続年数や業種ごとの相場を参考にしつつ、中小企業退職金共済や養老保険の利用も念頭に入れ、従業員が満足できる退職金を設定しましょう。
これから退職金を出す企業が減るにつれて、福利厚生として退職金があるというのは大きなアドバンテージになります。
経営者の方はそれも踏まえ、しっかりとした退職金制度を設けましょう。