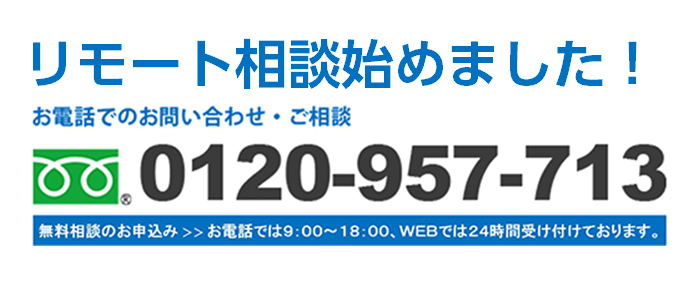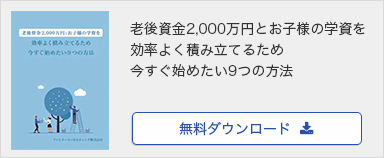退職金規程は、従業員に退職金を支給する際の指針を定めるものです。
従業員の福利厚生の一環として退職金の制度を整える時に、退職金規程をきっちり作っておくことをおすすめします。
そこで重要なのが、作っておくメリット・必要性はどのようなものか、何について定めれば良いのか、業績が悪化した場合に変更・廃止して良いのか、などといったことです。
この記事では、それらのことについて、ポイントを押さえて分かりやすく説明します。また、最後に実際の規程例も紹介します。
The following two tabs change content below.
私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。
1.退職金規程の役割と必要性
退職金規程は、退職金の制度がある雇用主において、従業員等に支給する退職金の金額や支給基準、支給時期、手続等について定めたものです。
実は、法令上は退職金規程を定めておく義務はないのです。
しかし、いったん定めたら、就業規則の一種なので、法的な拘束力を持ちます。
また、主に以下の3つの観点から、事実上、定めておくべきものと言えます。
- 従業員側とのトラブルを防ぐ
- 従業員の勤労意欲を引き出す
- 税務調査の際の説明がスムーズになる
それぞれについて説明します
1.1.従業員側とのトラブルを防ぐ
まず、退職金の支給基準、手続等を明確にしておくことで、従業員とのトラブルを防止することです。
たとえば、以下のようなことです。
- 勤続年数に応じて金額に差をつける
- 自己都合退職の場合は一定の減額をする
- 懲戒解雇等の場合は支払わないことにする
退職した従業員から訴訟を起こされるなど、法的なトラブルに発展するのは面倒なものです。
実際、従業員が退職後に勤務先を訴えるケースが急増してきています。
常識的に考えて当たり前だと思われるようなことであっても、できる限り明確に定めておく必要があります。
死亡退職金の場合は盲点!
また、在職中に亡くなった従業員のための「死亡退職金」の制度がある場合は、亡くなった従業員の遺族との間で、退職金の額等について紛争になることがあります。
典型的なのは、法人が福利厚生のため従業員に養老保険(1/2損金の福利厚生プラン)をかけていたケースです。
詳しくは後ほど改めてお伝えしますが、この場合、制度上、従業員の遺族が死亡保険金を直接、保険会社に請求するしくみになっています。
そこで、法人の側で「死亡退職金=養老保険の死亡保険金」だと定めておかないと、遺族側が別に会社に死亡退職金を支払えと請求してくる可能性があるのです。
退職金規程はこのようなトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
1.2.従業員の勤労意欲を引き出す
次に、従業員に老後資金に対する安心感を与え、勤労意欲を持ってもらうことです。
「老後2,000万円問題」に象徴されるように、高齢化社会の中で、老後の生活資金をどう準備するかが深刻な問題になっています。
そんな中、退職金制度を整備することは、従業員の老後の安心を確保することに伝わります。
退職金制度のような福利厚生を充実させることにより、優秀な人材を確保し、勤労意欲を引き出し、ひいては会社の発展にもつながります。
そのためには、せっかくの退職金制度を、誰もが分かるように明示しておく必要があります。
退職金規程を定めることによって、周知徹底しておくことができます。
1.3.税務調査の際の説明がスムーズになる
企業には税務調査が何年かに1回入ります。
たとえば、ある従業員に退職金を支給したタイミングで税務調査が入った場合に、退職金規程があれば、退職金の支給基準や金額についてスムーズに説明ができます。
退職金規程がないと否認されるか?
「退職金規程がないと退職金の損金算入が否認される」というのは誤りです。
しかし、退職金規程としての体裁がなく慣行にとどまる場合、どのような基準で支給しているのか根拠を示すことが難しくなります。
また、退職金規程がない場合、税務上は退職金ではなく「特別ボーナス」として給与扱いされる可能性があります。
そうなると、社会保険料がかかり、かつ、退職者の側では給与所得として扱われることになります。
退職所得が給与所得よりも税制優遇されていることについては「退職金にも税金がかかる?覚えておきたい退職所得の基礎知識」をご覧ください。
功績ある従業員だけの特別の「退職金」は?
では、退職金の制度自体がない企業で、特に功績のある従業員に対してだけ特別に退職金・功労金を支給する場合はどうでしょうか。
このようなケースでは、その従業員を特別扱いすべき理由を合理的に説明ができ、かつ、退職金の額が不相当に高額でないことが必要です。
ただし、税務上は退職金ではなく「給与」扱いされる可能性があります。やはり退職金規程を作成しておくことをおすすめします。
2.退職金規程で定めるべき事項
退職金規程で定めておくべき重要な事項は以下の通りです。
- 対象となる従業員の範囲
- 金額の算定基準
- 不支給・減額の条件
- 支給時期
- 死亡退職金についての定め
- 退職金制度自体を改定または廃止する場合の要件
それぞれについて説明します。
2.1.対象となる従業員の範囲
まず、対象となる従業員の範囲です。最低限、以下の事項について定めておく必要があります。
- 正社員のみか、パート・アルバイトの人まで含めるか
- 最低の勤続年数を定めるか
また、従業員が昇格して役員になった場合にどう扱うかということも重要です。たとえば、役員と従業員とで別の制度を設けるのであれば、それも明記しておく必要があります。
2.2.金額の算定基準
退職金規程を定める場合、もっとも重要なのが、退職金の支給額の基準です。
中小企業の場合、もっとも一般的なのは、勤続年数により一定額を決め、職位等により「功労加算」をする方法です。
最近はやりのポイント制は?
ただし、最近「ポイント制」というのが注目されてきています。人事評価や内部資格等、在職中の様々な要素を「ポイント」化して積み上げ、ポイントに応じて退職金額を支給するものです。
ポイント制はきめ細かな人事管理が前提となっているため、どちらかと言えば大企業向けの制度です。
中小企業でも、人事評価制度や内部資格制度が確立している企業であれば、導入しても良いかもしれません。
2.3.不支給・減額の条件
不祥事を起こした従業員を解雇する場合(懲戒解雇、諭旨解雇等)の退職金を不支給・減額にするならば、その旨を定めておく必要があります。
2.4.支給時期
退職する月に支払うのか、それとも退職から一定期間経過後に支払うのか、といったことも、定めておく必要があります。
2.5.死亡退職金についての定め
退職金の制度を定める場合、同時に、従業員が在職中に亡くなった場合に遺族に「死亡退職金」を支払う旨の定めも設けることになります。
算定基準は、基本的に通常の退職金(生存退職金)に準じることになります。
ただし、死亡退職金特有の事項として、以下のようなものが挙げられます。
- 死亡退職金の額を生存退職金よりも多く設定する
- 業務上の死亡とそれ以外とで金額に差を設ける
- 死亡退職金を支払う親族の範囲
- 死亡退職金の支給時期
生命保険・退職金共済の場合の注意点
生命保険や共済を活用する場合、保険金や共済金が保険会社から直接遺族に支払われるしくみにすることがあります。
典型的なのは養老保険の「福利厚生プラン」や中小企業退職金共済です。
これらの場合、遺族が別途、企業に退職金を請求してくる可能性があります。
そこで、保険金・共済金を「死亡退職金」として扱う旨も定めておく必要があります。
2.6.退職金制度自体を改定または廃止する場合の要件
最後に、退職金制度は、あくまでも福利厚生の一環です。企業の業績が悪化するなどして福利厚生どころではなくなってしまう可能性があります。
しかし、退職金規程はいったん定めると就業規則の一部をなし、従業員との間で法的拘束力が発生します。
変更する場合には原則として従業員の同意が必要です。
それを避けるには、以下の事項を明確に定めておく必要があります。
- 社会情勢・経済状況の変動により退職金の制度の縮小や廃止ができること
- その場合には従業員の同意が不要であること
3.労働基準監督署への届出の手続
上でお伝えした通り、退職金規程を定めた場合、法的には就業規則の一部と扱われます。したがって、労働基準監督署への届出が義務付けられています。
以下の書類を2部ずつ揃え、労働基準監督署の窓口に提出します。
4.退職金規程の例
最後に、退職金規程の例を掲載します。
ここまでお伝えしてきたことをどのように実際の規程に反映させれば良いのか、参考にしていただければと思います。
第1条(適用範囲)
この規程は、就業規則の規程に基づき社員の退職金について定めたものである。
この規程による退職金制度は、会社に雇用され勤務する正社員に適用する。パートタイマー、嘱託など就業形態が特殊な者についてはこの限りではない。
第2条(退職金の算定方法)
退職金は別表で定めるところにより、退職時における基本給の月額に社員各人の勤続年数に応じた退職金支給率を乗じて得た額とする。
前項の算定を行うにあたって、その者の退職事由が次の第1号から第4号までのいずれかに該当する場合には退職金支給率の甲欄(※省略)を、第5号および第6号のいずれかに該当する場合には乙欄(※省略)をそれぞれ適用する。
- ①定年
- ②事業の縮小など業務上の都合による解雇
- ③業務上の事由による傷病
- ④死亡
- ⑤自己都合
- ⑥業務外の事由による傷病
第3条(計算期間)
計算の対象となる勤続年数は、入社日から起算し、退職の日までとする。これには試用期間を通算するが、就業規則に定める休職期間についてはこれを通算しない。
計算上1年未満の端数月が生じた場合は、15日以上を1ケ月とし、月割計算を行う。
第4条(特別功労金)
在職中、特に功労があったと認められる社員に対して、退職金に特別功労金を加算して支給することがある。支給額は、その都度その功労の程度を勘案して定める。
第5条(支払の時期および方法)
退職金は、退職または解雇の日から30日以内に通貨で直接、支給対象者にその全額を支払う。
ただし、その者の同意がある場合は、その指定する金融機関口座への振込みまたは金融機関振出小切手などの方法により支払う。
第6条(遺族の範囲および順位)
本人死亡のときの退職金を受ける遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第42条から第45条までに定めるところによる。
第7条(退職金の不支給)
以下の各号の一に該当する者には、退職金を支給しない。ただし、事情により第2条に規定する自己都合退職金支給額に相当する退職金を支給することがある。
- ①就業規則に定める懲戒規定に基づき懲戒解雇された者
- ②退職後、支給日までの間において在職中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が発見された者
退職金の支給後に前項第2号に該当する事実が発見された場合は、会社は支給した退職金の返還を当該社員であった者または前条の遺族に求めることができる。
第8条(社外業務に従事した場合の併給の調整)
出向等社命により社員が社外業務に従事し、他社より退職金に相当する給付を受けた場合には、その者の退職金は、この規程により算定された退職金から当該給付に相当する額を控除して支給する。
第9条(退職金の積立方法と支給方法)
会社が、中小企業退職金共済制度など外部機関において積み立てを行っている場合は、当該外部機関から支給される退職金は、会社が直接本人に支給したものとみなし、第2条に規定する算定方法により会社から直接支給する退職金は、当該外部機関から支給される退職金の額を控除した額とする。
第10条(退職金規程を改定する条件)
会社の経営状況および社会情勢の変化等により必要と認めた場合、従業員の同意なくして支給条件・支給水準を見直すことがある。
まとめ
退職金規程は、法令上定める義務はありません。しかし、従業員側とのトラブルを防止する意味でも、従業員の勤労意欲を引き出す意味でも、税務調査の時の説明をスムーズにする意味でも、作成しておくべきものです。
退職金で定めなければならない主な事項は、以下の通りです。
- 対象となる従業員の範囲
- 金額の算定基準
- 不支給・減額の条件
- 支給時期
- 死亡退職金についての定め
- 退職金制度自体を改定または廃止する場合の要件
退職金規程はいったん定めると、就業規則の一部として法的拘束力を持つことになるので、財源の確保も含めて慎重に整備することをおすすめします。