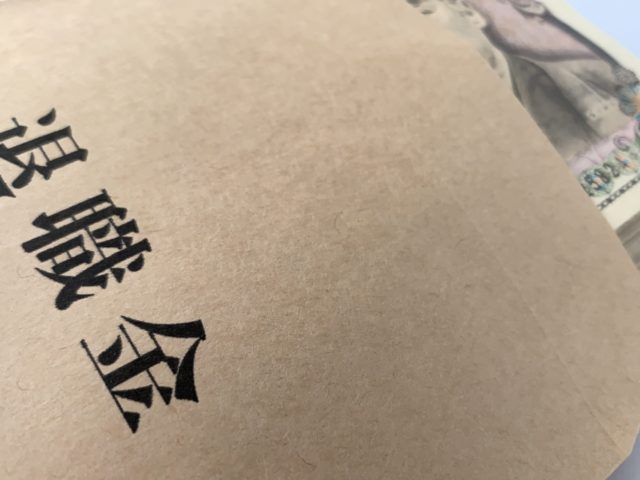経営者・役員の方の退職金の制度を整える場合、金額はいくらにすればいいのか、どういう手続をとればいいのか、といったことが気になることと思います。
高すぎると会社の経費(損金)として認められませんし、きちんとした手続を踏まないと、やはり損金として認められません。
そこで、この記事では、退職金の額の決め方と、支給するために必要な手続について、分かりやすく整理してお伝えします。
The following two tabs change content below.
私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。
1.役員退職金はいくらにすればいいのか
数億円の支給も可能!節税効果絶大の役員退職金の効果的な活用方法
まず、役員退職金の額をいくらに設定すれば良いのかという基準についてお伝えします。
実は、退職金の額には制限がありません。しかし、会社の経費つまり損金に算入できる額が限られています。
そこを超えた分については、法人税を納めなければなりません。
それではまず、退職金はどれくらいまでなら損金に算入できるでしょうか。以下、お伝えします。
1.1.基本は「功績倍率法」で計算する
一つの方法が、同じ地域の同業種・同程度の規模の他社の役員退職金の額を参考にすることです。これができればベストです。
ただし、ちょうどいい規模の同業他社が周囲にあるとは限りません。
そこで、よく用いられるのが、「功績倍率法」です。
通常、以下の計算で決定します。
最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率=役員退職金
在任年数
まず、「在任年数」を計算に入れるのは、会社を維持・発展させるために一生懸命に働いてきたという重要な目安の一つだからです。
功績倍率
次に、「功績倍率」です。これは、役位が偉くなるほど高くなります。なぜなら、役位が上がれば経営に対して負う責任が大きくなるからです。
功績倍率の例は以下の通りです。
- 社長 3.0
- 専務 2.5
- 常務 2.5
- 取締役 2.0
- 監査役 2.0
以下の例で計算してみましょう。
- 役職:代表取締役社長
- 在職期間:25年
- 最終報酬月額:100万円
- 功績倍率:3倍
100万円×25年×3倍=7500万円となります。
1.2.他と比べて高すぎなければOK
ただし、この計算式が絶対というわけではありません。
たとえば、最終の報酬月額を働き盛りの頃よりも低く抑えてある場合など、厳密にこの計算式を使うと退職金の額が極端に低くなってしまうようなケースも考えられます。
そこで、実際には、そういったケースで30%程度の「功労加算」が行われることがあります。
また、あくまでも、税務署が目を光らせているポイントは、同じ地域の他の同業・同規模の会社と比べて高すぎないかということです。
功績倍率法の計算はそれを判断するための重要な材料ではありますが、必ずしも絶対視されているわけではないということです。
2.退職金を支給するための手続
次に、役員退職金を支給するための手続について簡単にお伝えします。
退職金の支給の手続は、最低限、株主総会で退職金の金額または計算方法を決議して、それに基づいて支給すれば良いことになっています。
ただし、役員退職金の制度のある会社の多くは、「役員退職金規程」を作成して、客観的な基準を明らかにしています。
これは、税務当局から退職金の損金算入を否認されるリスクをあらかじめ摘み取っておけるというメリットがあります。
なお、役員退職金規程に定めた額よりも低い額しか支給しないことも、役員本人の同意があればOKです。
退職金規定に関しては役員退職金を損金に算入するため押さえるべき4つのポイントで解説していますので、是非参考にしてください。
まとめ
役員退職金の金額自体は法令で制限されていません。ただし、退職金を会社の損金算入できるかは、制限があります。
損金に算入できる限度額は、基本は「功績倍率法」で計算すれば良いでしょう。
ただし、重要なのは他の同業種・同規模の会社と比べて高すぎないかということですので、功績倍率法で計算した金額が低すぎるならば、「功労加算」等を行うことも考えられます。
また、「役員退職金規程」を作成しておくことをおすすめします。これは、基準を明らかにするだけでなく、税務当局から否認されるリスクを抑えることにもつながります。