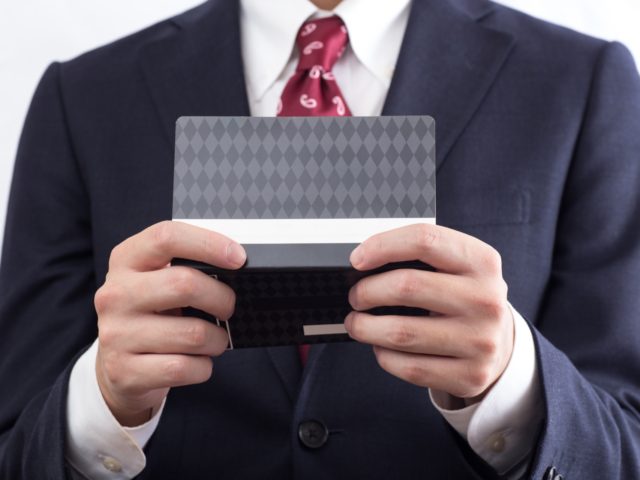2006年から有限会社にとって代わり、新たな会社の形として登場した合同会社。
近年ではAppleやGoogle、身近なところではスーパーの西友などが合同会社の形を採っており、どんどん世の中に浸透してきています。
amazonなど、わざわざ株式会社から合同会社に鞍替えする企業もあるほどです。
今回はそんな合同会社を設立する上で、株式会社とどのような違いがあるのか、比較しながら紹介していきます。
それぞれ有利な点、不利な点が存在するので、それらをしっかりと把握しつつ、自身が起業する際にどちらの形を採るべきか、よく考えてみましょう。
The following two tabs change content below.
私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。
はじめに|合同会社とは
まずは合同会社がどのようなものなのかを紹介します。
合同会社は、2006年以降登場した会社の形の1つです。
株式会社で一番偉いのは、出資者である「株主」なのですが、合同会社では、「経営者=出資者」なので、経営者が一番偉いということになります。
結果として、合同会社では株式会社よりも柔軟な経営が可能です。
1.合同会社設立の流れ
合同会社設立までの流れは、以下のようになります。

株式会社と比較すると、株式発行の手続き がないため、手続きが簡単になっています。
株式会社の場合は、会社の基本事項を決める際、資本金を元に、
- 株主と株主が出す出資金の割合
- 株の金額
- 株の発行数
- 発行可能株式総数
を決定する必要があり、合同会社に比べ手続きが複雑です。
では、合同会社設立の流れを詳しく見ていきましょう。
1.1.個人事業廃止の届出
まず、個人事業の廃止手続きです。
以下の書類を税務署に提出することで、個人事業主としての営業を廃止できます。
- 個人事業の開廃業等届出書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 事業廃止届出書
申請すると、その年の1月1日から会社の設立日までが個人事業主としての営業期間となり、翌年に確定申告をすることになります。
1.2.会社の基本事項決定
会社の基本事項として、以下の項目を決定します。
その他、会社の印鑑や印鑑証明書の準備が必要です。
1.3.商号の調査
似た商号がないかを、法務局で調査します。
悪気もなしに付けた商号が似ているからと、使用差し止め要請や損害賠償の請求が来てしまったら、たまったものではありませんね。
そのような事態を避けるためにも、商号調査は重要です。
1.4.定款作成
会社の定款を作成します。
定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」が定められており、1つも抜け落ちてはいけません。
合同会社の「絶対的記載事項」は以下の通りです。
- 事業目的
- 商号
- 本店所在地
- 社員(出資者)の氏名・住所
- 社員(出資者)の全員を有限責任にするという内容
- 社員(出資者)の出資の目的及びその価額または評価の基準
漏れのないように注意しましょう。
1.5.出資金の払込み
会社の代表である代表社員の個人口座に、社員(出資者)が定款に記載された通りのお金を振り込みます。
通帳に記録を残さなければならないため、代表社員自身も振り込みを行う必要があります。
利用する口座はすでに利用しているものでも問題ないのですが、上記のことも考え、新たに開設した口座を利用した方がおすすめです。
1.6.合同会社設立登記の申請
法務局に登記申請をします。
申請してから登記完了までにかかる期間は、数日〜2週間程度です。
登記申請をした日が会社の設立日になります。
登記が完了すれば、晴れて会社設立です。
1.7.合同会社設立後の各役所への届出
会社設立後にもやることは残っています。
人を雇い入れる予定があるなら雇用保険や社会保険などの加入手続きが必要ですし、税務関係の手続きも必要です。
また、法人設立後であれば、法人名義の銀行口座やクレジットカードを作ることもできるようになります。
上記のような手続きを終えれば、ついに会社としての第一歩を踏み出すことができるわけです。
2.株式会社との違いについて
違い①:経営方針の決定や利益の分け前について
上述のように、株式会社で最も強い権利を持つのは、「株式」を購入した「株主」です。
「株主」は具体的に、以下のような権利を持つことになります。
- 会社の方針などを決める「株主総会」に出席し、意見できる権利
- 「配当金」などの利益分配を受け取る権利
- 会社が解散する際に、会社に残っている資産を分配して受け取る権利
重要なのは、これらの権利が、持っている株式の「割合」によって変わることです。
例えば、Aさんが400万円出資し、Bさんが600万円出資した、資本金1,000万円の株式会社があったとします。
この場合、AさんとBさんの出資額の割合は2:3ですね。
すると、上記の権利についても割合が2:3になります。
つまり、「株主総会」での発言権はBさんの方が強く、配当金についても、Bさんが全体の60%と、多く受け取ることが出来るのです。
万一会社が加算することになった時も、得られる資産はBさんが60%、Aさんが40%になります。
このように、最初に出資した金額によって、権利の割合が決まってしまうのが、株式会社の特徴です。
たいして合同会社では、配当金の分け前や会社の方針に意見する権利について、「割合」を自由に決めることができます。
出資額と関係なく、出資者=経営者がどれだけ会社貢献したかなど、単なるお金以外の部分で柔軟に権利の割合を決められることが、合同会社の最大の特徴と言えるでしょう。
違い②:設立費用や運営コストについて
合同会社は株式会社と比べ、設立費用や運営コストがお手頃です。
そのため設立のハードルが低く、起業を考えている個人事業主などには、株式会社より選ばれることが多くなってきています。
会社の設立には、以下のようなお金が必要です。
- 登録免許税
- 収入印紙代
- 公証人手数料
- 定款の謄本手数料
株式会社と合同会社で上記の金額を比べてみましょう。
①株式会社の場合
- 登録免許税:15万円
- 収入印紙代:4万円
- 公証人手数料:5万円
- 定款の謄本手数料:2,000円
- 合計:242,000円
②合同会社の場合
- 登録免許税:6万円
- 収入印紙代:4万円
- 公証人手数料:0円
- 定款の謄本手数料:0円
- 合計:100,000円
上記の通り、株式会社と合同会社では、設立時の費用に約14万円もの差があります。
この金額差だけでも、起業の際に合同会社を選ぶ理由になりますよね。
株式会社では役員に任期があり、期限が切れる度に「重任登記」をしなければなりません。
その際手数料として1万円(資本金1億円以上なら3万円)必要なのですが、合同会社にはそもそも役員の任期がないため、そのような手数料が必要ないのです。
加えて、決算の公告義務もないため、公告手数料である年間3~6万円の費用が節約できます。
違い③:社会的な信用について
会社員の方はあまり意識することがないかもしれませんが、自営業及び企業にとって、社会的信用というものはかなり重要なものとなってきます。
銀行から融資を受ける、事務所を借りるといった際に、必ず注目されることになるからです。
そんな社会的信用については、株式会社の方が有利であるといえます。
近年設立数が伸びているとはいえ、合同会社は株式会社と比べ、まだまだ知名度が低いです。
信用という部分では、古くから会社の形としてある株式会社に勝ることは出来ません。
設立の際には、その点をしっかり把握しておいた方が良いでしょう。
まとめ
ここまで合同会社と株式会社の違いを比べつつ、設立する上でどのような点が優れているのかを紹介してきました。
最も違いが出るところといえば、やはり会社方針の決定の早さでしょう。
「出資社=経営者」である合同会社では、外部からの意見を待つことなく方針を決定できます。
変化の大きな業種や小規模な会社では、そういった小回りの良さが重宝されるでしょう。
また、出資金額によって権力に差が出ないというもの大きなポイントで、ある種の独裁が起こることもなく、自由な経営が可能になっています。
設立費用の安さも大きなポイントです。
特に税負担の悩みから法人化を考えているような個人からすれば、起業にかかるコストが少なければ少ないほど良いわけです。
個人事業主が増えている近年の状況からすると、合同会社の増加は、今後さらに増加していくことでしょう。
株式会社と合同会社の違いをしっかり理解し、自分に合った会社を作り出すことが大切ですよ。