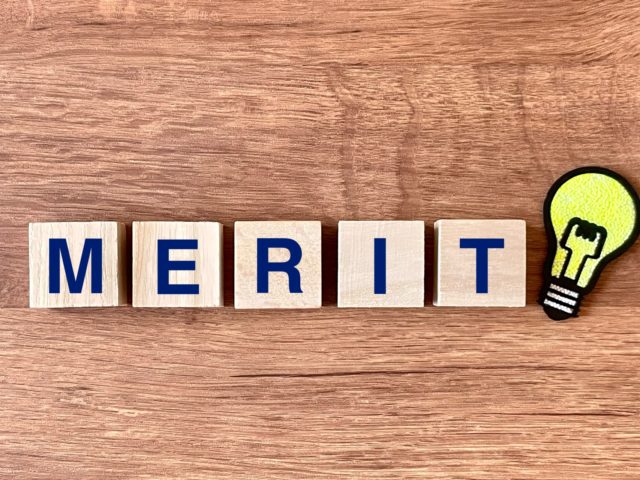近年、株式会社に代わり、起業の際に選ばれるようになってきた合同会社。
起業を考えている個人事業主からすると、設立のハードルが低いと言われている合同会社とメジャーな株式会社、どちらが良いのか、気になっている方も多いでしょう。
実は合同会社には、設立のハードル以外にも様々なメリットがあります。
わざわざ株式会社から合同会社に鞍替えする大手企業もあるほどです。
今回はそんな合同会社のメリットについて、
- 株式会社と比較した際のメリット
- 個人事業主と比較した際のメリット
に分けて説明していきます。
しっかり把握した上で、自営業に徹するか起業するか、起業するなら株式会社と合同会社のどちらにするのか、身の振り方を考えてみましょう。
The following two tabs change content below.
私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。
はじめに:合同会社とは
合同会社とは、2006年の会社法改正によって登場した、比較的新しい会社の形です。
会社の形として最も代表的なものと言えば株式会社ですが、合同会社は、特に零細企業やスタートアップに有利なポイントを多く持っており、年々数を増やしています。
自由な働き方として会社員よりも個人事業主を選ぶ、という人が増えてきている近年において、節税の面で法人化を考える個人からすると、合同会社が持つメリットは大変魅力的です。
また、その大きなメリットを得るために、AmazonやGoogle等の大手企業も、合同会社という形を選んでいます。
1.株式会社と比較した際のメリット
では、合同会社には実際にどのようなメリットがあるのか、まずは株式会社と比較しながら見ていきましょう。
1.1.設立のハードルが低い
合同会社は以下の点から、株式会社より会社設立のハードルが低くなっています。
- 設立費用が安い
- 運営コストが安い
順番に見ていきましょう。
①設立費用が安い
会社設立の際には、以下のような費用がかかります。
- 登録免許税
- 収入印紙代
- 公証人手数料
- 定款の謄本手数料
株式会社の場合、上記の費用として合計24万円ほど必要です。
開業資金としてこれだけのお金がかかると考えると、それなりに身構えてしまいますよね。
対して合同会社では、これらの費用が10万円程度に抑えられており、株式会社と比べ、約14万円もの差があります。
これだけでも合同会社の設立のハードルが、株式会社より低いというのがよく分かりますね。
②運営コストが安い
株式会社では役員に任期があり、期限が切れる度に「重任登記」をしなければなりません。
その際手数料として1万円(資本金1億円以上なら3万円)必要なのですが、合同会社にはそもそも役員の任期がないため、そのような手数料が必要ないのです。
また、株式会社には決算の内容を公表するという義務があります。
この際、手数料として3~6万円が必要です。
対して、合同会社では決算の公告義務がありません。
年間3~6万円の費用が節約できると考えると、始めたての会社にはうれしいメリットです。
以上の2点から、合同会社は株式会社より運営コストが安く、起業に踏み切りやすくなっています。
1.2.経営の自由度が高い
株式会社で最も強い権利を持つのは、株を購入した「株主」です。
「株主」にはお金さえ払えば誰でもなることができ、今後の運営方針を決める「株主総会」に出席することができます。。
つまり、会社の内情を知らない外部の人間でも「株主」となり、運営方針に意見することが出来るのです。
また、株主総会での発言権の強さは、「株主」持っている株の割合によって決まります。
外部の人間が株を多く持っている場合、その人の意見を飲まなければなりませんし、そもそも「株主総会」が終わらなければ、その年度の経営方針が打ち出せないわけです。
合同会社の場合は、「出資者=経営者」となります。
また、株という概念がないため、株主総会を開く必要もありません。
すなわち、設立当初にありがちな運営方針の変更などを、外部から邪魔されることなく、スピーディーに行うことが出来ます。
さらに、株式会社では出資額の割合に応じて権利の強さが決まりますが、合同会社では自由に決めることが出来ます。
つまり、出資額が少ない人にも平等な発言権を持たせることが出来るということです。
以上のような経営における自由さも、合同会社の大きな魅力といえるでしょう。
2.個人事業主と比較した際のメリット
2.1.所得税率が超過累進課税ではなくなる
個人の所得税は「超過累進課税」という税率を使って計算されます。
「超過累進課税」とは、所得の金額が大きければ大きいほど、税率が高くなる制度です。
個人の所得金額によって税率と控除額は以下のように変わります。
 対して合同会社のような会社の場合、所得は法人税の課税対象となり、「法定実効税率」という税率を使って計算されます。
対して合同会社のような会社の場合、所得は法人税の課税対象となり、「法定実効税率」という税率を使って計算されます。
法人の場合、資本金額が1億円以下であれば、「課税所得金額(益金−損金)」が、
- 800万円以下の場合→15.0%
- 800万円以上の場合→23.9%
となります。
個人と会社を比較すると、収入が「330万円〜6,949,000円を超える場合」と「900万円以上の場合」は、会社の方が所得にかかる税金が少ないことが分かりますね。
上記のような金額帯の収入を稼ぎ出している個人事業主の方は、法人化を考えてみるのも良いでしょう。
2.2.様々な税金対策ができる
上記の所得税にとどまらず、法人化することで様々な「税金対策」を行うことが出来ます。
詳しくは「会社の税金|効果的な節税対策をするためのテクニック」をご覧ください。
2.3.社会的信用を得られる
残念ながら個人事業主は、社会的信用を得にくいという話をよく聞きます。
会社員の時には当たり前に出来ていた賃貸の契約やクレジットカードの発行などで、審査になかなか通らず、驚いたという人も少なくないです。
合同会社として起業することで、個人事業主よりも多くの社会的信用を得ることができ、銀行からの融資なども引っ張りやすくなります。
ただし、株式会社と比べてしまうと信用度は低く、起業間取引などでは株式会社ほどの信用を得ることは出来ません。
その分設立費用の安さなど、ハードルの低さがあるため、株式会社より手軽に信用を得られると考えれば大変魅力的です。
まとめ
合同会社のメリットについて、株式会社、個人事業主と比較して紹介してきました。
株式会社と比べたうえで有利な点は、設立のしやすさと経営の自由度です。
手頃な設立費用は、個人事業主が起業する際に大きな助けになるでしょうし、年間のコストが抑えられるという点も、起業してからじわじわと効いてくることでしょう。
また、外部の出資者がいない合同会社は、会社の方針をスピーディーに決定することが出来ます。
これは株式会社の経営陣でも羨ましいと感じるところでしょう。
個人事業主と比較すると、税金対策や社会的信用の部分で、有利な点が多いといえます。
税負担については、今回紹介した所得税にとどまらず、様々な施策を行うことが出来ます。
合同会社のメリットを良く把握した上で、前向きに企業を考えてみてはいかがでしょうか。