次のようなことでお悩みはありませんか?
・自分の会社にピッタリのサイバーリスク保険を選んで加入したい
・現在加入中のサイバーリスク保険の補償内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
もしも、サイバーリスク保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

サイバーリスク保険は、会社が個人情報漏えい事故を起こしてしまった場合の損害賠償金等の費用や、サイバー攻撃でシステムが停止してしまった場合の損害等を補償してもらえる保険です。
あなたの会社は、顧客名簿やIC決済、クレジットカードにダイレクトメール、SNSやネットショッピングなど、大量の個人情報を日常的に扱っていると思います。そんな個人情報が流出してしまい、釈明会見のニュースを見て危機感を覚えた方も多いのではないでしょうか?
ハッカーにより攻撃された、委託先の従業員により持ち出しされた、自宅に持ち帰ったところ紛失してしまった・・・。あなたの会社に害意はありませんから、起きてしまったこれら事象については被害者かもしれません。ところが、流出させてしまった個人の方にとってあなたの会社は加害者でしかないのです。したがって、損害賠償責任を問われることになってしまうリスクがあります。
今日は、そういう個人情報漏えい事故、サイバー攻撃事故に備えてあなたの会社を守る「サイバーリスク保険」についてお伝えしていきます。
資産防衛の教科書編集部
最新記事 by 資産防衛の教科書編集部 (全て見る)
目次
サイバーリスク保険で重要なのは、以下の3つの補償です。
漏えい事故の訴訟で発生した賠償金や訴訟費用はもちろん、実際に情報漏えいが起きていなくても、危機管理対応に必要となった費用を補償してくれるのが特徴です。
サイバーリスク保険で最も重要なのが、情報漏えいによって損害賠償を負った場合の補償です。もしもあなたの会社が漏えい事故で損害賠償を負うことになった場合、その賠償金の額が保険金として受け取れるのです。保険会社の了承を得た場合には、弁護士費用や訴訟費用、調停、示談費用なども対象となります。
個人情報を漏らした企業が「誠意を表して欲しい」、「納得のいく賠償をして欲しい」として、集団訴訟を起こされることは珍しくありません。
高額事例として、2007年2月のTBCグループの事件に関する裁判例があります。
エステサロンのチェーンを経営する会社で、顧客の個人情報を管理していたウェブサイトがアクセス制限されていませんでした。そのため顧客の個人情報を無関係な第三者が見られる状態になっており、ファイル交換サービスを通じて世界中にばらまかれてしまったという事例です。
流出してしまった個人情報には、氏名・住所・電話番号・生年月日・職業だけでなく、スリーサイズやコース内容、身体の悩みまで含まれていました。そればかりでなく、いたずら電話や迷惑メール、DMが送付されるなどの二次被害が発生しました。そのため、会社は1件あたり慰謝料3万円と弁護士費用5,000円、総額231億円の損害賠償を命じられました。
このように、いったん個人情報漏えい事故が起きると、あなたの会社は巨額の損害賠償を負ってしまうリスクが大きいのです。したがって、損害賠償金の補償は、サイバーリスク保険の最も重要な補償内容と言えるでしょう。
次に、被害を最小限にとどめるために支出した費用等が補償されます。これを「サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項」と言います。例えば、お詫び状の作成費用、臨時開設するコールセンターの委託費用などが対象となります。また、セキュリティ事故により消失したデータの復元費用なども対象となります。
なかでも、見舞金や見舞品として購入した金券の購入費用も対象になるのは大きなメリットです。1人当たりの金額は500円~10,000円程度にすぎなくても、サイバーセキュリティ事故の場合、総額だと大変な額になります。
ネットワーク機能が停止したために得られなかった利益の損害や、そんな中で営業を継続するためにかかった費用も補償されます。事故がなかったならば計上することができた営業利益の額や、収益減少を防ぐために使った費用が対象です。
サイバー攻撃があった時の対応に慣れている人などいないでしょう。対策や調査はどのようにしたら良いか?被害者への対応はいつ、どのように行うのが良いのか?被害を拡大させない為にも、迅速な初期対応が必要です。そんな時、経験豊富な保険会社がサポートしてくれます。
コールセンターの設置や広報対応、被害拡大防止の措置や原因究明に至るまで、事故対応の様々なことをサポートしてくれます。また、事故対応のみならず、セキュリティ体制の診断や、事故が起こった場合の被害想定額を算出してくれたりもします。
2016年1月からマイナンバー制度が導入されました。それに伴って、サイバーリスク保険の重要性は、これまで以上に高まっています。
どういうことかというと、これまで、個人情報の管理義務は、5000件以上を扱う事業者のみが対象でした。ところが、マイナンバーは全ての企業、団体、個人事業主に管理義務が発生します。扱う情報量や企業規模の大小は問いません。
マイナンバーには、年金、健康保険、税金等、様々な個人情報が紐づいています。ですから、不正に扱われるリスクが非常に高いのです。しかも、マイナンバーは流出した場合の罰則が定められています。
したがって、あなたの会社も、事故を起こさないように管理体制を強化するのはもちろん、事故が起きてしまった場合に備えてサイバーリスク保険に加入することで、対策を万全にする必要があるのです。
これまで、サイバー攻撃のターゲットは大企業でした。ところがマイナンバー制度が導入されると、狙いはセキュリティ対策が不十分な中小企業へとシフトされています。むしろ、それほど個人情報を扱ってこなかった事業者であるからこそ、狙われやすくなっているのです。
一度流出してしまった情報は、安易に消去することは出来ません。現状、万全な対策であっても、ハッキング手法は日々進化しています。
サイバーリスク保険は、事故の賠償などの金銭的な補償はもちろん、対応や原因究明に対する補償
もあり、いざという時には企業の大きな味方となります。また、事故が起きないよう、最新の方法や各種対策に関する情報も教えてくれます。
次のようなことでお悩みはありませんか?
・自分の会社にピッタリのサイバーリスク保険を選んで加入したい
・現在加入中のサイバーリスク保険の補償内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
もしも、サイバーリスク保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
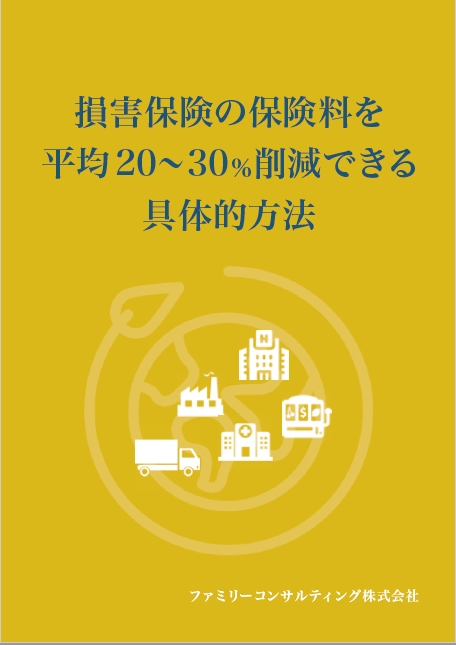
私たちは、他社にはない独自のノウハウで、数々の会社様の損害保険の保険料を削減してきました。
まず、論より証拠、以下はその事例のほんの一部です。いずれも補償内容はそのままに、保険料の大幅な削減に成功しています。
この無料Ebookでは、私たちがお手伝いしたコスト削減の事例をご紹介します。
そして、業種別に、むだのない最適な保険の選び方をお伝えします。
ぜひ、今すぐダウンロードしてください。
すぐに知りたい方は、0120-957-713までお問い合わせください。

友人など、他人の自動車を運転中に万が一事故を起こしてしまった場合、自動車を貸してくれた人の保険を使うことになれば、さらにその相手に迷惑をかけてしまうことになります。 そんな時に役立つのが他車運転特約です。 他車運転特約とは、他人の自動車を一時的

自宅の屋根の一部が損壊するなどして雨漏りした場合、火災保険の補償で修理費用がまかなえる可能性があるのはご存知でしょうか。 火災保険は火災だけでなく、雨漏りの原因になるような台風や大雪などの損害も補償の範囲に含まれているからです。 ただし、すべて

火災保険は、住む家があれば必ずと言っていいほど加入するものなので、人生の中でも長期にわたって付き合うことになる保険です。 だからこそ、結婚、離婚や相続といったタイミングで、契約者の名義を変更する機会が発生します。 名義変更を行わないと、物件の所

火災保険の評価額とは、火災保険の補償の対象となる建物・家財の価値を示す金額です。いざ建物や家財に損害が発生した場合に、受け取れる保険金の算定の基礎となるものです。 ただ実際、評価額とはどんなものかや、どのように定めればよいか分からない、という方が多い

火災保険にはさまざまな特約があり、補償の範囲を広げたりカスタマイズしたりすることができます。 しかし、パンフレットや保険会社のサイトを見ただけでは、それぞれの補償内容がどうなっているかということや、その特約が必要か不要かということはすぐ判断できないこ

地震保険は地震大国日本において、重要度の高い保険といえます。 しかし、分譲マンションの場合、マンションを建て直すほどの保険金をもらえるわけではないため、必要ないと考える人も多いようです。 実際のところ、マンションであっても、地震保険は被災時の生

企業の福利厚生制度を手厚くすることは、従業員の勤労意欲と安心感を高めることにつながります。 それにより、生産性向上や長期の継続雇用につながるだけでなく、人材採用の強化の後押しも期待できます。 企業の福利厚生制度の1つにGLTD(団体長期障害所得

「火災保険の保険金で、自己負担なしで屋根修理ができる」と勧誘する業者をよく目にします。 それをきっかけに、屋根が損傷した場合に、火災保険で修理ができないか検討する方も多いようです。 結論から言うと、屋根修理の費用を火災保険でカバーできるとは限り

自動車保険には「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」の3つの名義があり、それぞれ意味・役割が異なっています。 そのため、必要に応じて、それらの名義を変えなくてはなりません。 また、特に記名被保険者の名義変更の場合、自動車保険の割引率を示す等級

現在は、住宅ローンを組む条件として、金融機関から火災保険を契約するよう指示されることは少なくなっています。 しかし、住宅ローンを組むのであれば、火災保険の加入は必要です。もし加入していないと、何かあった場合に大きな後悔をする可能性が高いのです。