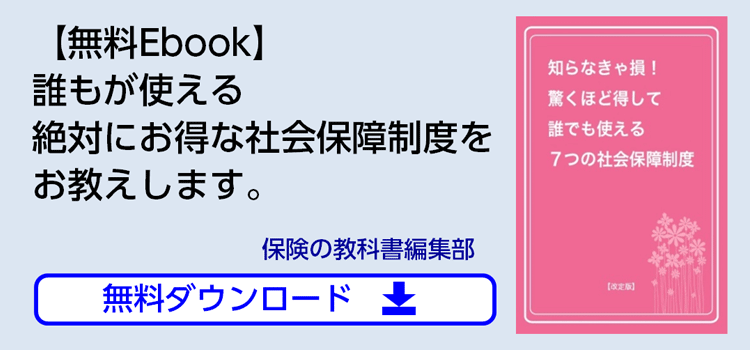火災保険では、損害保険金の金額をあらわす「新価」「時価」いずれかを選択します。
このうち「新価」を選べば十分な額の保険金を受け取れますが、「時価」では保険金が足りなくなり、おすすめできません。
この記事では、火災保険の保険金額を決める「新価」とは何かということと、必要な保険金を無駄なく受け取るために必要な火災保険の契約内容の組み方のポイントについて解説しています。
The following two tabs change content below.
私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。
1.火災保険の損害保険金の金額を決定する「新価」とは?
火災保険の「新価」とは、補償対象となる建物や家財(家電・家具・衣類など)の資産価値から、損害保険金の金額を決定する評価方法の1つです。
新価で評価される場合、補償の対象となる建物や家財を、改めて調達するのに必要な金額の損害保険金が用意されることになります。
つまり「新価」で評価されれば、損害保険金だけで建物を建て直したり家財を再購入したりすることができるということです。
1-1.「新価」の金額を決定する「評価額」とは?
火災保険の「新価」が損害保険金の金額をあらわす評価方法の1つであり、新価であれば損害保険金だけで建物や家財を改めて調達できることは書きました。
それでは「新価」での評価とはどのように行われるのでしょうか?
その際の基準となるのが、火災保険の「評価額」です。評価額とは簡単に言うと、火災保険の補償対象となる建物や家財の価値を表す金額です。
たとえば自宅の建物を建築するのにかかる建築費が2,000万円だとすれば、評価額も2,000万円ということになります。
火災でその建物が全焼した場合には、新価で評価すると損害保険金の金額も2,000万円です。
評価額=新価となるわけです。
なお、新価での損害保険金の算出方法は、場合によってもう少し複雑になります。詳細は後述します。
火災保険を契約する時には、損害保険金の上限額(保険金額)を決めるために、建物や家財の評価額を申告する必要があります。
ただし、契約時の書類やパンプレットなどが手元にないなどで、建物の建築費がいくらかわらない、あるいは家財の評価額をいくらに設定すればいいかわらない、といったこともあるでしょう。
次の項では、建物・家財(家具・家電・衣類など)それぞれの評価額の算出方法を解説します。
2.建物評価額の算出方法
建物の評価額の算出方法は、以下の3つに分類されます。
- 一戸建ての新築物件の場合
- 一戸建ての中古物件の場合
- マンションの場合
以下、それぞれ簡単に解説します。
2-1.一戸建ての新築物件の場合
新築の一戸建てでは、購入時(建築時)にかかった費用の総額から土地代と諸経費を引いた金額が、建物の評価額となります。
とはいえ土地・建物を一緒に購入する建売であると、建物の価格はわからないかもしれません。
その場合、売買契約書に記載されている消費税額をもとに、以下の計算式で建物評価額を算出することができます。
建物評価額=消費税額÷消費税率
この数式で建物の評価額がわかるのは、土地代金が消費税の課税対象外であるためです。
売買契約書に記載されている消費税額は、全て建物の金額にかかっています。
2-2.一戸建ての中古物件の場合
中古物件の建物評価額は、建築年と新築時の建物の価格がわかるかどうかで計算方法が違います。
以下、それぞれの場合を解説します。
2-2-1.建築年と新築時の建物の価格が分かる場合
建物の価格に対して建築年により求められる専用の指数(建築費倍率)をかけあわせる「年次別指数法」を使い算出します。
年次別指数法では、物価の変動などが建物評価額に反映されます。
また建築費倍率は毎年見直されるため、算出する際に確認が必要です。
年次別指数法の算出方法は、以下の通りです。
新築時の建物の価格 × 建築費倍率 = 建物評価額
たとえば新築時の建物の価格が3,000万円、建築費倍率が0.9であれば、建物評価額は以下のように算出されます。
3,000万円×0.9=2,700万円
年次別指数法は建築時の建物の評価額を使うため、より実態に即した正確な評価が可能です。
2-2-2.建築年と新築時の建物の価格が分からない場合
建物の構造・所在地といった条件をもとに導き出された1㎡あたりの標準的な建築費(新築単価)に、建物の延床面積をかけあわせる「新築費単価法」を利用します。
具体的な計算式は以下の通りです。
新築費単価 × 延床面積 = 建物評価額
たとえば新築費単価が12万円で延床面積が150㎡であれば、建物評価額は12万円×150㎡=1,800万円となります。
なお新築費単価法で算出された結果は、あくまで標準的な建築費をもとに算出された概算であるため、実態に近づけるため保険会社と相談の上で±30%の範囲で調整されます。
2-3.マンションの場合
マンションの購入価格には、専用部分の建物の価格だけでなく土地代や共有部分の価格も含まれています。
一方で建物評価額に該当するのは、専有部分の建物の価格だけです。そのため、前述の新築費単価法によって、建物評価額を算出します。
たとえば新築費単価が10万円で、延床面積(専有面積)が70㎡であれば、建物評価額は以下のように算出されます。
10万円×70㎡=700万円
3.家財評価額の算出方法
家財評価額は、「積算評価」「簡易評価」どちらかの方法で算出します。
積算評価とは、補償すべき家財とその金額を全てリストアップし合計する方法です。
シンプルな方法ではありますが、自宅にある家財(家電・家具・衣類など)を全てリストアップし、その価格を全て正確に確認するのは大変な手間がかかるため現実的ではありません。
そこで、一般的には「簡易評価」が使われます。
簡易評価とは世帯主の年齢や世帯人数、敷地面積などに基づき、保険会社がまとめた目安額を使う方法です。
以下、参考までにA損保の簡易計算表を紹介します。
|
単身世帯
(面積無関係) |
2人以上世帯(延床面積) |
| 20㎡未満 |
20㎡~
30㎡未満 |
30㎡~
40㎡未満 |
40㎡~
50㎡未満 |
| 世帯主年齢 |
29歳以下 |
290万円 |
290万円 |
360万円 |
420万円 |
490万円 |
| 30歳~34歳 |
290万円 |
390万円 |
480万円 |
560万円 |
650万円 |
| 35歳~39歳 |
290万円 |
540万円 |
660万円 |
780万円 |
900万円 |
| 40歳~44歳 |
290万円 |
660万円 |
800万円 |
940万円 |
1,080万円 |
| 45歳~49歳 |
290万円 |
750万円 |
910万円 |
1,070万円 |
1,230万円 |
| 50歳以上 |
290万円 |
790万円 |
960万円 |
1,130万円 |
1,300万円 |
この表によって目安を割り出した上で、「うちは世帯人数が少ないからもう少し減らしていいか」とか「高価な家財が多いから金額を増やすか」といった調整をするわけです。
4.保険金額を評価する「時価」とは?
火災保険の保険金を評価する金額には「新価」のほかに「時価」があり、火災保険の契約時にどちらを選ぶか決めることになります。
その上で「時価」とは、「新価」から経年劣化などで落ちた品質の分の金額を差し引く保険金の算出方法を指します。
たとえば新価で算出された建物に対する保険金の金額が3,000万円であり、経年劣化により500万円分の品質が落ちていたとしましょう。
このとき、この建物が全焼した場合に時価で算出される保険金の金額は以下のようになります。
3,000万円-500万円=2,500万円
くわえて新価で支払われる損害保険金の金額は、ほかにも物価上昇も影響します。
物価上昇まで含めた算出方法については次の項で解説します。
4-1.新価・時価それぞれでの詳しい損害保険金の算出例
新価・時価で損害保険金を算出する場合、上述した評価額以外に物価上昇や経年劣化の影響が加味されます。
実際にどんな算出がされるか以下の例でみてみましょう。
【建物が全焼した場合に支払われる損害保険金の例】
- 10年前に建物を新築した際の建物の建築費(評価額)は4,000万円
- 新築時と同等の建物を再築する場合は、物価上昇の影響により現在は4,500万円が必要
- 経年劣化により建物の価値が1,000万円分下がっている
上記条件にもとづき新価で損害保険金が算出される場合、「同等の建物を再築するのに必要な費用」を補償するわけですから、支払われる損害保険金の金額は4,500万円です。
次に時価で損害保険金が計算される場合は、新価から経年劣化分の金額が差し引かれることになります。
具体的には以下のように計算されます。
4,500万円(新価で算出される損害保険金の金額)-1,000万(経年劣化により下がった分の価値)=3,500万円
4-2.新価と時価では新価を選ぶべき
前項までで解説した通り時価で算出すると、火事で建物が全焼した場合など損害をカバーするのに損害保険金だけでは足りなくなる可能性が高いです。
前項の例では、1,000万円足りない計算になります。
実際にどのくらいの金額が足りなくなるかは経年劣化の程度によって異なるため一概には言えませんが、時価で損害保険金が算出されるとなると、ただでさえ災害にあって負担の大きい時にさらに自己負担を迫られることになります。
これでは、いざというときの助けになるべき保険としてはその価値が半減してしまいます。したがって、火災保険では、新価で損害保険金が計算されるように契約時に設定すべきです。
5.古い火災保険では「時価」が選ばれている場合が多い
火災保険の新価・時価について解説しましたが、最近の火災保険では契約者が意識しなくても保険会社が「保険金額=新価」で設定してくれることがほとんどのようです。
ただし必ずしもそう設定されるとは限らないので、このように設定すべきことを覚えておいて損はないでしょう。
また、1988年の保険料自由化以前に加入した火災保険に関しては時価が選ばれていることが多いので注意してください。
しかも2015年9月まで火災保険の保険期間は最長で35年まで選択できたため(現在は10年)、古い火災保険の契約が更新されずに残っている可能性もあります。
心配な場合は、保険証券等で確認するようにしてみてください。
まとめ
火災保険において「新価」とは、火災などによって損害を受けた建物や家財を、再築・修理・再購入するのに必要な金額を指します。
そのため火災保険の契約時に、新価で保険金が算出されるようにしておけば、いざというときに必要な金額の保険金を受け取ることが可能です。
一方の時価は、経年劣化によって下がった価値の分だけ新価から保険金が引かれるので、保険だけでは建物や家財の損害を補うのに足りない可能性が高いです。それでは、いざというときに困ることになるためおすすめできません。
また保険金の上限額(保険金額)は、新価と同額にすべきです。そうすれば必要な金額を、保険料の無駄なく受け取ることができるからです。