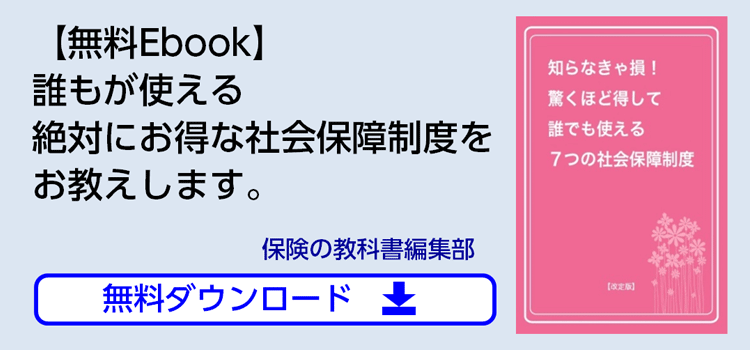マンションを借りる契約をしたり、購入したりする際には火災保険に入ることになりますが、保険料の相場はどのくらいか、どんな補償内容が適切なのか気になっていませんか?
この記事では、そもそもマンションにおいて火災保険はどんな役割を果たすのか解説した上で、事例をもとに火災保険料の相場がどのくらいか紹介しています。
The following two tabs change content below.
私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。
1.はじめに|マンションの火災保険で何が補償される?
マンションの火災保険の相場を見る前に、火災保険の補償内容を簡単におさらいしておきましょう。
1.1.補償されるのは「自分が起こした火災」だけではない
火災保険は、自分自身や家族が自室で火災を起こしてしまった場合だけでなく、近隣住民等が原因で類焼してしまった場合に発生した損害も補償してくれます。
なお、このような「もらい火」が発生した場合、日本には「失火責任法」という法律があって火元に対して損害賠償を請求することができません。
それが故意もしくは寝たばこのように故意と同視されるような過失でない限り、火元には賠償責任はないというのが失火責任法の内容です。
損害を受けた側の火災保険によって、補償を求める必要があります。
1.2.「家財」(家具・家電・衣類など)
火災保険が補償するのは建物というイメージが強いのではないでしょうか。
実際には建物はもちろんのこと「家財」も補償対象となります。
家財とは、自室から「持ち出せるもの一般」を指し、具体的には家具・家電・衣類・食器類・寝具・書籍などさまざまな物が該当します。
火災等の損害を受けた際には、家財にも大きな損失が出ますが、その分を火災保険が補償してくれるというわけです。
1.3.火災以外の事故・災害も補償
火災保険と聞くと、火災による損害のみをカバーする保険にも見えますが、以下のように、実際にはその他の事故・災害も補償対象としています。
- 落雷:落雷により生じた損害の補償
- 水災:台風による洪水など「水」に関する損害の補償
- 風災:台風による強風など「風」に関する損害を補償
- 水濡れ:漏水による損害を補償
- 盗難:盗難に遭った場合の損害を補償
- 破損等:うっかり事故による損害を補償(例:重い家具を運んでいてあやまって壁にぶつけ、穴を空けてしまった)
最近では火災保険のことを「住まいの保険」などと呼ぶ保険会社もありますが、このように住まいに対する総合的な保険であることは理解しておいた方がよいでしょう。
1.4.地震保険・個人賠償責任保険などをセットできる
火災保険は、ほかの保険をセットにして加入されることが多いです。
たとえば地震による損害を補償する地震保険は、火災保険とセットでしか加入できません。
また自室の漏水で階下に損害を与えてしまった場合など、第三者に対する賠償を補償してくれる個人賠償責任保険も、火災保険にセットされることが多い代表的な保険です。
火災保険の必要性や相場について考える時は、これらの保険がセットになることを知っておきましょう。
1.5.分譲か賃貸かで建物の補償の内容が異なる
マンション向けの火災保険の場合、分譲か賃貸かで、「建物」の補償の内容が異なります。「家財保険」「個人賠償責任保険」については、分譲・賃貸ともに変わりません。
|
分譲向けの火災保険
|
賃貸向けの火災保険
|
- 建物(専有スペース)の損害に対する補償
- 家財保険
- 個人賠償責任保険
|
|
まず分譲の場合、居室(建物の専有部分)は自分の所有物なので、自分で火災保険をかけて補償(建物(専有スペース)の損害に対する補償)を確保することが必要です。
これに対し、賃貸の場合、居室自体(建物)は貸主の財産で自分自身のものではないので、建物の補償を自分自身で付ける必要はありません。ただし、自室で火災を起こしてしまった場合等は、貸主に対して損害賠償をしなくてはなりません。したがってその賠償金等をカバーするために「借家人賠償責任保険」を付けなければならないのです。
賃貸マンションの火災保険は、分譲マンションのような「建物(専有スペース)の損害に対する補償」が不要な代わりに、「借家人賠償責任保険」をセットにしなければならないのです。
2.マンションに住む場合、火災保険に加入する義務はある?
マンションで暮らす場合、火災保険へ加入しなければならないのでしょうか?
この点についても簡単に振り返っておきましょう。
2.1.分譲マンションであれば自由
まず分譲マンションであれば、火災保険への加入は任意です。
ただし、もし加入していないと、火災をはじめとしたさまざまな損害に対する補償も失うことになるので注意しましょう。特に、ローン購入の場合、途中で建物が焼失してしまったとしてもローンの返済義務は残るので、火災保険は必須です。
上述したように、自分で気を付けることができない「もらい火」による損害も、火災保険があれば補償されます。
2.2.賃貸マンションの場合は加入が義務
賃貸マンションの場合、ほとんど、借家人賠償責任保険が付いた火災保険への加入が義務になっています。
なぜなら、貸主からすれば、もし借主の落度によって建物に損害が発生した場合、借主から損害賠償金を確実に取れなければ困るからです。
2.2.1.不動産会社がすすめる火災保険に加入しなくてもよい
賃貸マンションの火災保険は、不動産会社がすすめる商品にそのまま加入することが多いです。
しかし、実は、貸主が求める補償内容の条件さえ満たしていれば、自分で好きな保険会社を選んで加入することができます。
自分で賃貸マンションの火災保険を選ぶ時の選び方については「賃貸住宅で火災保険が義務である理由と自分で選ぶ時のポイント」をご覧ください。
3.マンションの火災保険の相場はどのくらい?
それでは、マンションの火災保険の保険料の相場はどのくらいでしょうか? ここでは、相場を決める要因について説明した上で、いくつかの事例を紹介します。
3.1.【前提】火災保険の相場は何で変わるのか
火災保険の相場を知るためには、保険料がどのような要因で変動するのか、知っておく必要があります。
火災保険の保険料を決める要因は、大きく分けて以下の3つです。
例えば補償内容を絞れば保険料は割安になりますし、保険期間は長い方が保険料が安くなります。
また、建物に防火対策が施されている場合、火災のリスクが少なくなるので、これも保険料が割安になる要因となります。
ただし、保険料を安くしたいという理由だけで補償内容を絞ったり、何も考えずに補償内容を決めてしまうと、災害に対応しきれず、保険に入っていた意味がなかったということになりかねません。
自身が所有する建物の立地などを考えつつ、建物ごとに合った補償内容を見定め、無駄のない内容に洗練していくことが大切です。
3.1.1.補償内容
まず重要なのが、どんな損害をどこまで補償してもらえるかです。
カバーされる範囲や補償の範囲が広いと、その分保険料が高くなります。
損害の発生原因
火災や風災に始まり、水災から水漏れ、果ては窃盗や車での当て逃げなどの人災まで、火災保険は様々な災害に対して補償を付けることができます。
火災保険の保険料を最も左右するのがこの部分です。特に吟味対象になりやすいのが、水災の補償の要否です。
建物が建っている土地が大きな河川の近くや山間部であれば、洪水などのおそれがあるので、水災の補償は必須と考えられます。
これに対し、高台にある一軒家やマンション・アパートの上階部分ならば、洪水等による被害のおそれは考えにくいので、水災の補償は必要性が低いと考えられます。
発生した損害をどこまでカバーしてもらえるか
最後に、損害が発生した場合にどこまでの範囲をカバーしてもらえるかです。
火災保険は基本的に、実際に発生した損害を限度額まで補償してもらえます。
限度額の基準になるのは、建物・家財の評価額です。
評価基準には、「新価(再調達価額)」と、経年劣化を計算に入れた「時価」の2種類がありますが、今日ではほとんどの契約が「新価」となっています。
特約
次に、オプションで付けられる「特約」です。
建物や家財自体の損害以外の諸費用を補償してくれる「臨時費用補償特約」や、自宅で火災が起きて火が近隣の家に燃え移って燃えてしまった場合に、その損害を補償してくれる「類焼損害補償特約」などがあります。
特に注目したい特約が、「個人賠償特約」です。
これは、誤って他人をケガさせてしまったりして、治療費等の損害賠償責任を負った場合に、それを補償してくれる特約です。
たとえば、自転車で歩行者にぶつけてケガをさせてしまった場合などに補償してくれる便利な特約で、保険料もそれほど高くありません。
A損保の火災保険の「個人賠償責任補償特約」だと、月々170円で、国内なら無制限、国外なら1億円まで補償してくれます。
「個人賠償特約」は、基本的に自動車保険と火災保険の特約としてのみ加入できるものなので、どちらかには必ずつけることをおすすめします。
3.1.2.建物の種類・構造
建物の種類や構造も保険料の額に影響します。「構造級別」と言い、「M構造」、「T構造」、「H構造」の3種類に分かれます。
この3種類を分けるのは、ごく大ざっぱに言ってしまえば、「燃えやすいか燃えにくいか」です。
建物が「一戸建て」か「共同住宅」か、柱が何で出来ているのか、耐火構造になっているのか、などによって、保険料に違いが出てくるのです。
分類は全ての保険会社に共通で、「M構造」「T構造」「H構造」の3種類です。
M構造⇒T構造⇒H構造、の順に燃えやすくなり、それにつれて火災保険の保険料が高くなっていきます。
| 構造級別 |
条件 |
| M構造 |
共同住宅(マンション・アパート)で、鉄筋コンクリート造等、耐火性のある素材で造られたもの |
| T構造 |
①戸建て住宅で、鉄筋コンクリート造等、耐火性のある素材で造られたもの
②鉄骨造の集合住宅で、耐火性に関する基準(耐火構造・準耐火構造等)をみたさないもの
③木造の共同住宅・戸建て住宅で、耐火性に関する基準(耐火構造・準耐火構造等)をみたすもの |
| H構造 |
木造の一戸建て・共同住宅で、耐火性に関する公的な基準を一切みたさないもの |
自分の家の構造がどれにあたるかは、持ち家の場合は家の売買契約書または建築工事請負契約書、借家であれば賃貸借契約書から分かります。
3.1.3.保険期間
保険期間の長さも保険料を決める要因の一つです。
火災保険は、自動更新制で、最長10年の保険期間が設けられており、長期であるほど保険料が安くなります。
例えば保険期間を30年とした場合、更新までの期間は1~10年までの間で選択することが出来るのですが、1年ごとに更新するより、10年ごとの更新にしたほうが割安になるということです。
つまり、同じ30年でも、
- 保険期間5年で6回更新
- 保険期間10年で3回更新
を比べてみると、同じ補償内容でも、2の方が安くなるというわけです。
こまめに保険の内容を見直したい人は、細かく更新するのも1つの手ですが、最初の加入時に内容をしっかり吟味して、最長期間の10年で契約するのが賢明でしょう。
3.2.マンションの火災保険契約例
それでは火災保険料の例をみていきましょう。
A損保の火災保険の契約を例に、まずは分譲マンションの場合から紹介します。
●分譲マンションの場合
- 構造級別:M構造
- 所在地:東京
- 築年数:新築
- 床面積:80㎡
- 建物保険金額:(火災保険)1,600万円、(地震保険)800万円
- 家財保険金額:(火災保険)500万円、(地震保険)250万円
- 補償される事故:火災、落雷、破裂/爆裂、風災、雹(ひょう)災、雪災、水災、水濡れ、外部からの物体落下等、騒擾(そうじょう)、盗難、破損・汚損
- 個人賠償責任特約:3億円
- 保険期間:10年(地震保険5年)
- 払込方法:長期一括払
この場合の保険料は270,380円(火災保険10年分・地震保険5年分)で、火災保険は1年あたり16,127円、地震保険は1年あたり10,868円です。
補償の範囲から「水災」を外すと、保険料は237,720円(火災保険10年分・地震保険5年分)となり、10年で32,660円安くなる計算です。
●賃貸マンションの場合
- 構造級別:M構造
- 所在地:東京
- 築年数:10年
- 家財評価額:500万円
- 補償される事故:火災、風災、雹(ひょう)災、雪災、水ぬれ、外部からの物体落下等、騒擾(そうじょう)、盗難
- 借家人賠償特約:5,000万円
- 個人賠償責任特約:1億円
- 契約期間:2年
この場合、保険料は2年間で19,070円(家財5,960円、借家人賠償特約9,550円、個人賠償特約3,560円)です。
水災の補償を外していますが、水災を付けた場合は2年間で23,130円(家財10,020円、借家人賠償特約9,550円、個人賠償特約3,560円)となります。家財保険の保険料が2年間で4,060円高くなります。
4.火災保険の保険料を安く抑える方法
火災保険の保険料は、工夫をすることで安くおさえることもできます。
ここでは、そのためのポイントを5つ紹介します。
4.1.必要性の低い補償を外す
上述したとおり、火災保険の補償範囲は多岐にわたっています。
そこで必要性が薄い補償を外すことによって、保険料をおさえることができます。
たとえば河川から離れた場所であったり、マンションの高層階であったりする場合は、水災にあう可能性が低いので、補償から水災を外すといった選択肢があげられます。
4.2.家財に対する保険金額を最適化する
家財に対する保険金額もまた、火災保険の保険料を大きく左右する要素の1つです。
家財に対する保険金額は、一般的に保険会社が用意した「簡易計算表」を使って決めます。
これは世帯主の年齢や世帯人数、専有面積などによって保険会社が作成した相場表のようなもので、参考までにB損保の簡易計算表は以下のとおりです。
|
単身世帯 |
2人以上世帯(延床面積) |
| (面積無関係) |
20㎡未満 |
20㎡~30㎡未満 |
30㎡~40㎡未満 |
40㎡~50㎡未満 |
| 世帯主年齢 |
29歳以下 |
290万円 |
290万円 |
360万円 |
420万円 |
490万円 |
| 30歳~34歳 |
290万円 |
390万円 |
480万円 |
560万円 |
650万円 |
| 35歳~39歳 |
290万円 |
540万円 |
660万円 |
780万円 |
900万円 |
| 40歳~44歳 |
290万円 |
660万円 |
800万円 |
940万円 |
1,080万円 |
| 45歳~49歳 |
290万円 |
750万円 |
910万円 |
1,070万円 |
1,230万円 |
| 50歳以上 |
290万円 |
790万円 |
960万円 |
1,130万円 |
1,300万円 |
この表によれば、たとえば世帯主の年齢が31歳で世帯の人数が2人以上、延床面積が40㎡~50㎡ならば、家財に対する保険金額は650万円となります。
一見すると多過ぎるようにみえますが、テレビ・パソコン・冷蔵庫・洗濯機・パソコン(家庭により複数台)といった高額な家電だけとっても数十万円~100万円を超える場合も多いのではないでしょうか。
その他、ブランド物が多く含まれていたり、アウトドアグッズ・ゴルフ用具など趣味の品物にお金をかけていたりすれば、それだけ高額の保険金額が必要です。
とはいえ、家具・家財がそれほど多くなかったり、量販店で安く備えていたりするといった場合には、簡易計算表を参考にしつつ保険金額を抑えるのも1つの選択肢です。
4.3.保険期間をできるだけ長期にする
火災保険に限ったことではありませんが、保険期間を1年でなくできるだけ長くして、保険料を一括払にすることによって保険料を安くすることが可能です。
今回紹介した上記例では、保険期間を10年(一括払)としていますが、火災保険では1年から10年で保険期間を選択することが可能です。
実際、保険期間を長くしている方も多く、損害保険料率算出機構が公開した「2018年度 火災保険・地震保険の概況」によれば、最も多いのは5年(40%)という長期契約で、次に1年契約(29%)、2年契約(20%)、10年契約(7%)と続きます。
約半数は5年以上の長期契約にしている計算です。
4.4.個人賠償責任保険は重複しないようにする
個人賠償責任保険は火災保険以外にも、自動車保険やクレジットカードのオプションなどで契約することが可能です。
そのうえで、仮に重複して契約していたとしても、その分だけ多く補償が行われるわけではないため、保険料が無駄になってしまいます。
たとえば個人賠償責任保険の契約A・契約Bがあると仮定し、賠償すべき金額として1,000万円が発生したとしましょう。
この場合、契約Aの補償だけだったとしても、契約A・契約Bで2つ補償があったとしても、補償される額は1,000万円で変わりません。したがって、個人賠償責任保険に重複して加入するのは無駄です。
他に個人賠償責任保険がある場合は、そちらを解約して火災保険の個人賠償責任保険にまとめるのも1つの手です。
なぜなら、自動車保険の特約やクレジットカードのオプションとしての個人賠償責任保険は、それぞれ自動車を廃車したりクレジットカードを解約したりすると一緒に消滅してしまいますが、火災保険は住む場所がある限り必ず加入するものからです。
4.5.複数の保険会社の見積もりを比較する
火災保険は、同じ補償内容でも、保険会社によって保険料に差があります。できるだけ保険料を節約したい場合は、少し手間はかかりますが、複数の保険会社から見積もりをとって見比べてみるようにしましょう。
まとめ
マンションの火災保険は、自分が起こした火災のほか、もらい火や火災以外の災害(風災・水災など)でも補償を受けられます。また、建物だけでなく家財も補償の対象です。
その上で、保険料は、建物の構造や所在地、補償の範囲等によって異なります。「平均してこのくらい」とは言えませんが、一応の相場をお伝えしました。
この記事を参考に、過不足ない補償内容で加入するようにしていただけたら幸いです。