次のようなことでお悩みはありませんか?
・自分の会社にピッタリの店舗休業保険を選んで加入したい
・現在加入中の店舗休業保険の補償内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
もしも、店舗休業保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

店舗休業保険は、不意の災害や近隣での事故などによってお店を休業する事になった場合に、休業期間中の粗利益を補償してもらえる保険です。
店舗を運営されている方は、トラブルなどで大きな被害が出ないかと毎日不安な日々をお過ごしのことでしょう。店舗ではいつ何が起こるかわからず、店舗を閉めなければならなくなることも考えられます。
店舗休業保険は、そのようなリスクに備えるものです。
この記事では店舗休業保険のことをわかりやすくお伝えします。少しでも店舗を安心して運営できるよう加入を考えている方はぜひ参考にしてください。
資産防衛の教科書編集部
最新記事 by 資産防衛の教科書編集部 (全て見る)
目次
冒頭でもお伝えしたように、店舗休業保険は、お店が災害などにより休業した際に、その間の粗利益が補償される保険です。
店舗を経営されている人には必須といえる保険ですが、補償の対象や金額など不明点は大きいと思います。
具体的には以下が補償されます。
休業をしたときに補償してもらえるのは「粗利益」です。これは、簡単に言えば、「売上」から「原価」を差し引いたものです。
例えば販売価格1本100円のジュースを5,000本販売したら、「売上」は50万円です。そして、原価が1本50円であれば、「粗利益」は25万円になります。
この「粗利益」は人件費等も込みの額です。そこからさらに人件費等を差し引いたものを「純利益」と言います。
店舗休業保険が「純利益」にとどまらず「粗利益」まで補償する理由は、休業している間の人件費等を確保しなければならないからです。
保険金額の決め方は、「1日あたりの粗利益の額」以下で設定します。
そして、1日あたりの粗利益額は
年間粗利益額 ÷ 年間営業(操業)日数
で計算します。
ただし、額には上限があり、その上限は保険会社によって違いますので、設定するときは確認しましょう。
店舗休業保険は名前の通り、休業した時に補償してもらえる保険です。
休業の原因を問わず広く補償してもらえるのですが、まれに補償してもらえないケースもあります。
したがって、重要なのは補償されないケースを理解しておくことです。
仮に店舗が休業しても以下の場合は補償の対象外です。
故意に店舗を休業された場合はもちろん補償されません。
また、重過失つまり重大なミスは故意と同視されますので、それによって大きな損害が発生し、店舗が休業に追い込まれても補償の対象とはなりません。
こちらも当然といえますが、経営者はもちろん従業員の人が誤って店舗に車を突っ込み、店舗が休業状態になったとしても保険金は支払われません。
アクセルとブレーキの踏み間違えなど可能性はゼロではありません。
店舗休業保険は窃盗なども補償の対象となりますが、万引きによる店舗休業は補償の対象となりません。
万引きは悪質な犯罪行為であり、過去にも書店やスポーツ店など万引き被害により休業に追い込まれた店舗はありますが、店舗休業保険の対象にはなりません。
冷凍食品や海産物を取り扱う店舗の場合、冷凍庫で保管をすると思いますが、仮にスイッチが切れていて物品が全滅して休業に追い込まれても、補償の対象とはなりません。
これまで店舗休業保険についてお伝えしておきましたが、この保険がカバーしてくれるのはあくまでも店舗が休業した場合だけです。
それ以外にも、店舗を運営しているとさまざまなリスクがあります。したがって、ここでは、必要な保険の種類をご紹介します。
業種によって必要な保険は違いますが、特に重要なのは以下の保険です。
まず、店舗や設備、商品等の損害に備える必要があります。
そのために必要なのは「店舗総合保険」等の事業用火災保険です。特徴は、一般的な火災保険と比べて設備や商品の補償が手厚いことです。
ただし、商品については盗難は原則として対象外ですので、ご注意ください。
店舗などで製造したものが原因でお客様等に障害を負わせたり、財産に損害を与えたりしてしまった場合に、損害賠償金の額等を補償してもらえる保険です。
例えば飲食店で食中毒を出した場合や、小売店で販売したものでお客様がケガをした場合などです。
特に以下の店舗に必要とされます。
生産物賠償責任保険については『PL保険はなぜ必要?思わぬ賠償リスクからあなたの会社を守るための基礎知識』で解説していますので参考にしてください。
店舗などの施設の欠陥が原因で会社が損害賠償責任を負った場合、会社を揺るがすほどの経済的ダメージになる可能性すらあります。
したがって、多くの会社にとって施設賠償責任保険は大変重要な保険です。
特に以下の店舗に必要とされます。
施設賠償責任保険については『施設賠償責任保険とは?意外に知らない補償内容と必要性』で解説していますので参考にしてください。
受託者賠償責任保険とは、会社がお客様からお預かりした品物を誤って「壊してしまった」「汚してしまった」「紛失してしまった」「盗まれてしまった」等のため損害賠償責任を負った場合に、保険金が受け取れる保険です。
お客様から物をお預かりする店舗では必須と言えます。特に以下の店舗に必要とされます。
受託者賠償保険については「受託者賠償責任保険とは?対象となる会社と補償内容」で解説していますので参考にしてください。
店舗を運営しているとさまざまなトラブルが想定でき、万が一にも休業状態になった場合、売上が途絶え、経営者の方、従業員の方の生活も崩壊しかねません。
店舗休業保険に加入をしておくことで、店舗を営業できていたら得られていたはずの「粗利益」が補償されますのでおすすめします。
ただし、店舗休業保険はあくまでも休業したときに粗利益が補償されるものですので、店舗の建物や設備の損害の補償や、お客様に対しての補償はありません。
店舗を運営している方は、併せて、上記でお伝えした各種保険もご検討されることもおすすめします。
次のようなことでお悩みはありませんか?
・自分の会社にピッタリの店舗休業保険を選んで加入したい
・現在加入中の店舗休業保険の補償内容で大丈夫か確認したい
・保険料を節約したい
もしも、店舗休業保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
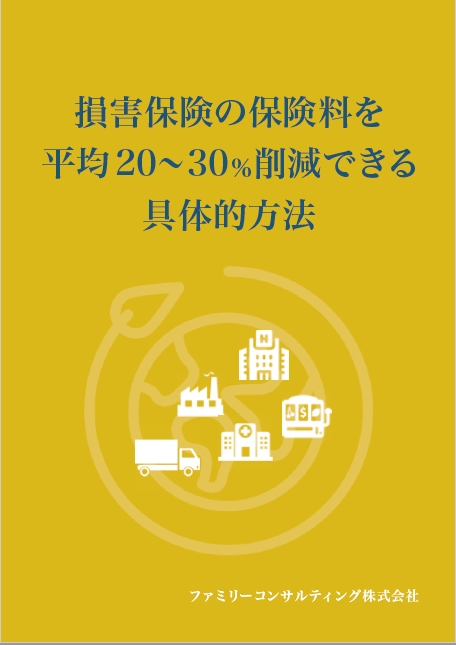
私たちは、他社にはない独自のノウハウで、数々の会社様の損害保険の保険料を削減してきました。
まず、論より証拠、以下はその事例のほんの一部です。いずれも補償内容はそのままに、保険料の大幅な削減に成功しています。
この無料Ebookでは、私たちがお手伝いしたコスト削減の事例をご紹介します。
そして、業種別に、むだのない最適な保険の選び方をお伝えします。
ぜひ、今すぐダウンロードしてください。
すぐに知りたい方は、0120-957-713までお問い合わせください。

「火災保険の保険金で、自己負担なしで屋根修理ができる」と勧誘する業者をよく目にします。 それをきっかけに、屋根が損傷した場合に、火災保険で修理ができないか検討する方も多いようです。 結論から言うと、屋根修理の費用を火災保険でカバーできるとは限り

企業の福利厚生制度を手厚くすることは、従業員の勤労意欲と安心感を高めることにつながります。 それにより、生産性向上や長期の継続雇用につながるだけでなく、人材採用の強化の後押しも期待できます。 企業の福利厚生制度の1つにGLTD(団体長期障害所得

自宅の屋根の一部が損壊するなどして雨漏りした場合、火災保険の補償で修理費用がまかなえる可能性があるのはご存知でしょうか。 火災保険は火災だけでなく、雨漏りの原因になるような台風や大雪などの損害も補償の範囲に含まれているからです。 ただし、すべて

火災保険にはさまざまな特約があり、補償の範囲を広げたりカスタマイズしたりすることができます。 しかし、パンフレットや保険会社のサイトを見ただけでは、それぞれの補償内容がどうなっているかということや、その特約が必要か不要かということはすぐ判断できないこ

火災保険は、住む家があれば必ずと言っていいほど加入するものなので、人生の中でも長期にわたって付き合うことになる保険です。 だからこそ、結婚、離婚や相続といったタイミングで、契約者の名義を変更する機会が発生します。 名義変更を行わないと、物件の所

現在は、住宅ローンを組む条件として、金融機関から火災保険を契約するよう指示されることは少なくなっています。 しかし、住宅ローンを組むのであれば、火災保険の加入は必要です。もし加入していないと、何かあった場合に大きな後悔をする可能性が高いのです。

自動車保険には「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」の3つの名義があり、それぞれ意味・役割が異なっています。 そのため、必要に応じて、それらの名義を変えなくてはなりません。 また、特に記名被保険者の名義変更の場合、自動車保険の割引率を示す等級

火災保険の評価額とは、火災保険の補償の対象となる建物・家財の価値を示す金額です。いざ建物や家財に損害が発生した場合に、受け取れる保険金の算定の基礎となるものです。 ただ実際、評価額とはどんなものかや、どのように定めればよいか分からない、という方が多い

地震保険は地震大国日本において、重要度の高い保険といえます。 しかし、分譲マンションの場合、マンションを建て直すほどの保険金をもらえるわけではないため、必要ないと考える人も多いようです。 実際のところ、マンションであっても、地震保険は被災時の生

友人など、他人の自動車を運転中に万が一事故を起こしてしまった場合、自動車を貸してくれた人の保険を使うことになれば、さらにその相手に迷惑をかけてしまうことになります。 そんな時に役立つのが他車運転特約です。 他車運転特約とは、他人の自動車を一時的